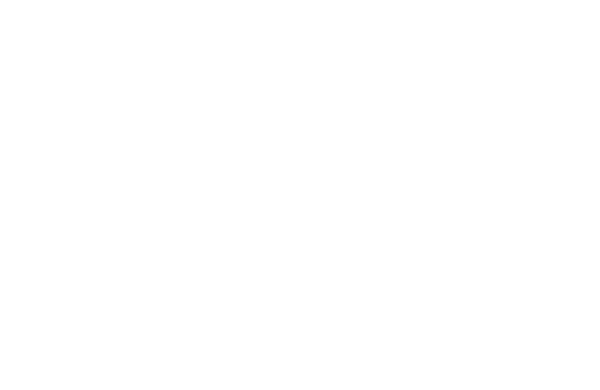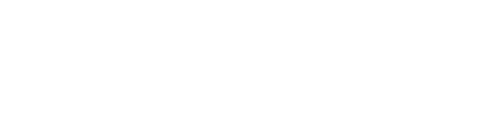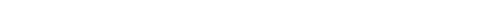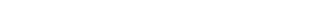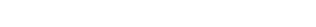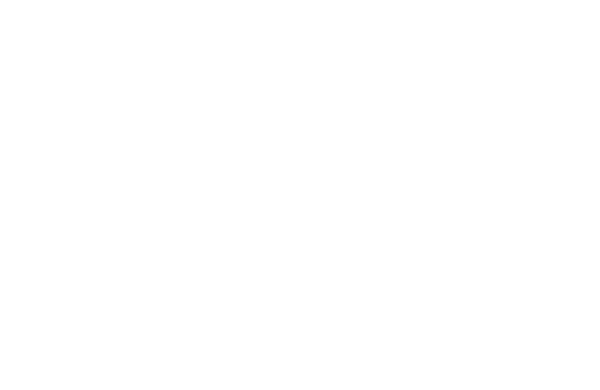


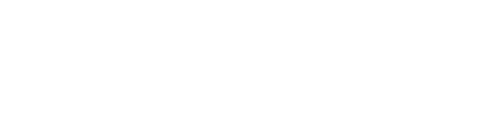
病みたまふ君
君が死の夢を見し日に裏山の藤の花のみ散り初めにけり
君が頬日の出づるかに染まりけり月は菜の花畑より出づ
十三のかの朝焼けは君と見き今は枯木のもとに来て見ゆ
病みたまふ頬の青さは海よりもなを深くして冬来たりけり
看護婦に声振るわせて君を訊く病舎の窓の湖(うみ)の青さよ
裏山に行きて死なむと思ふとき海へ行かむと云ひしを思ふ
昨日も今日も葦の花散る野に出(いで)てさめざめ泣けり月出(いづ)る迄
君がためひとり蒼ざめ裏山に来て月見草摘みし夜半かな
鬼灯(ほおずき)を鳴らし合ひつつ野を行きしいとけなき日を誰に語らむ
別れなる朝
君が頬の横には遠きエルムケップ連山のあり別れなる朝
別れなる朝に贈りしわが庭の花はかの花君影の花
君が家
君が家見むとて丘を登りつつ撫子摘めば腕に溢れぬ
秋風に荒家と化せし君が家夜毎に犬の遠吠える家
旅行く日
北風の船尾に立てば白鳥(しらとり)の群れこそ砕け散りゆく夕べ
青森の海の暮れゆくむなしさよ仰げば鳥の未だに飛べり
白鷺の城のごとくにあるゆえに秋草に寝て君を思はむ
盆太鼓
盆太鼓打つは恋知る若者にて哀しき音に鳴れるものかな
盆太鼓若者が打つは哀しくて胸の奥にも遠く聞こへり
秋の町
野分する公園の芝を駈けゆくは白き犬なり悲しきものなり
秋近き神社の森で拾ひたる白き電球を点けてみるかな
啄木の哀しみをもて飯食へば流るる涙の冷たくもあり
茸生えし草履下げては遠雷の夕べうなだれさまよひて来し
連山の凍り横たふそのもとに溶鉱炉静かに火を吐きてをり
月寒町よ
月寒の町に住むてふ病む君を一目見んとて急ぎ来しかも
初恋の人住むと云ふ月寒町に来は来つれども坂道続く
わが後を片目の犬が追(つい)て来ぬ月寒町の冬の坂道
冬来れば月寒町の裏通り哀しき歌を唄ひ歩めり
冬日暮れ月寒町の空のもと鴉など飛び我らさまよふ
冬日暮れ犬のさまよふ影が我が影に重なり坂を登れり
たそがれは見知らぬ町をさまよひてたどりつきたる冬の停車場
馬鈴薯の花
大いなる瞳を持てる君こそは雨の中なる馬鈴薯の花
啄木の恋の歌よりわが詠ふ歌哀しけれ馬鈴薯の花
桐の葉
裏山に桐の青葉のさやぐなりわが青春を育みし家
桐の葉に頬を埋めて初恋の後の傷みに堪ふるものかな
秋風
少年の淋しく揚ぐる凧の如き恋初めし日の秋風のわれ
死後我は盲魚と化すにあるらむと友に語る日秋風の吹く
青森の海のやふなるものが瞳(め)に漂ふことを友に語らむ
灯を慕ふごとくに君を慕ひをり虫の性(さが)かも魚の性かも
朝焼の人知れずして消ゆるごと君ひそかにも去りゆきにけり
エレムケップ連山に秋来たりけり眼を細むれば君を思へば
江別哀歌
石狩の北のはずれの町に来て君ら泣きたる冬のたそがれ
わが唄ふ江別哀歌の声細し夕べは君ら啜り泣くより
石狩の岸辺の町に哀歌聞く飢えつつ我らさまよひゆけば
淋しければ一番町のとある家我に灯ともす冬のたそがれ
雪國の小さき駅なる窓に頭(づ)を傾げて立てば涙流るる
宿命
わが胸に黒き小旗の烈風に靡くが如く心荒れをり
わが耳の裡(うら)にも銀河寒々と続くを思ひ口笛を吹く
犬橇の柩のなかに凝固せる己(おの)が額に雪の積れり
瞼閉づれど開けど冥さは同じなり夜病みたまふひとを思ふに
病むひとを思ひ夜空を仰ぐなり行く雲もなく飛ぶ鳥もなく
鳥辺野
無惨にも恋に破れて鳥辺野にさめざめ泣きに来し大工かも
鳥辺野に恋に破れて泣きに来し大工の紺の瞳を思ふ
清水
清水の塔に涙(さし)ぐみ君が名を櫻明かりにくちずさみけり
泣き濡れし君が手をとり清水の坂を下るや赤き日の暮れ
旅人
三日月の微光に濡れし君が頬半跏思惟の君なりしかな
嵐山黒き瞳にかなしみのひとすじ残る君なりしかな
剃刀研人
星の出に剃刀研人(かみそりとぎ)は月見草摘み摘み深き裏山行けり
裏山を剃刀研人は月見草しみじみ散るを見つつ急げり
星の出の名も無き山にしみじみと剃刀研人は月見草摘む
月見草生命(いのち)の如くはらはらと散りつつ我を悲しますかな
口笛
まっ青な夜空があれば口笛を北上夜曲吹き鳴らすかな
口笛吹けばいつしか哀歌となりにけり我には病むる人のありけり
蜉蝣
はらはらと草蜉蝣は野より野へはつかに消えし人の如くに
蜉蝣の薄きいのちを思ひつつ遠き野寺の鐘聴いてゐる
賀茂川
病む鴨の波に乗りつつ鳴くに似て君泣くは悲し酒を啜らむ
涙(さし)ぐみし瞳に浮ぶ賀茂川の水の色など美しかりき
遙かなる比叡の鐘を数へつつ人の恋しき夜となりにけり
四条橋君と渡れば三日月の東山より出(い)で初めにけり
春の夜の星数えつつ四条橋をみな子待ちし我を憐れむ
君がため涙流るる賀茂川の岸の菫(すみれ)は星屑なりき
春の傘
春の傘差してはるばる来つれども歌舞練場の朝のさみしさ
故なくに夕べ涙ぐみ春雨の歌舞練場の灯るを見たり
君が瞳
賀茂川の水の如くに君が瞳(め)の透きとほりつつ夜来たりけり
賀茂川の水を眺めて涙(さし)ぐみし君が瞳は水より暗し
秋の風
秋の風君が肩より南座の旗赤々と見え初めにけり
東山暮れゆきにけり秋風に南座の旗飜る見ゆ
東山下りて来れば秋風の南座の旗あかあかと見ゆ
賀茂川へ幻の君を連れあるく夕陽に映える南座の旗
京に来て淡き恋知る子となりし我を憐れみ秋の風吹く
泣きながら四条橋にて別れ来し君が名を呼ぶ浜千鳥かな
暗き星
君と来て東寺の塔の尖端のひときわ暗き星を見てゐる
祇園よさらば
はるばる来れば祇園は涙に濡れてゐる君は何処よ君は何処よ
春夕べ祇園横丁酔ひゆけばギタァを弾ける君が窓見ゆ
春雨に濡れて急げば舞姫の赤き袖さえ悲しかりけり
仄暗き傘の内より春雨に濡れし乙女の赤き袖見ゆ
如月の祇園に紺の雪降れり夕べ淋しく君を思ふに
祇園町花の匂ひをして雪の降り初むみれば涙流るる
泣き濡れし君がか細き指にこそ祇園の雪は散りかかりけり
君が胸に小雨降るなりわが胸に雪の降るなり祇園よさらば
アザリヤの花
アザリヤの花に童は涙(さし)ぐみぬ父の名を呼び母の名を呼び
夕な夕なアザリヤの花散りにけり愛しきひとは如何にあるらん
野花
紫の野花の茎を噛みにけり初こひびとは病みたまひつつ
花摘みに行きて帰らぬをみなごを思へば青き星出でにけり
君に逢はずて死なむと思ひ裏山行けば藤蕾みをり生きんと思ふ
幻の花
月の出を待つが如くに君を待つ君影の花匂ふ喫茶店
わが前に幻として君は在り幻の花匂ふ喫茶店
麗しくなりぬと君に囁きぬ珈琲の香に咽び初むれば
白藤の花が匂ふと囁かば頷きたまふ君なりしかな
君が髪梳けばさやけき藤の香の町に匂ふとわれ囁きぬ
君に逢ひ別れて来れば白藤の匂ひの髪に滲みてありけり
白藤の匂ひさやけき北の町別れて悲しき唄くちずさむ
裏山に藤の花咲く春来れば再び君に逢はむと思ふ
月見草野に咲く如く我もまた一人野に出て君を思はむ
月見草咲く野に出(い)でてひと思ふこの淋しさを誰に語らむ
何処となく笛の音聞こゆ初恋のひと吹くらむか花蔭にして
朝な朝な裏山藤の花散れり慕ひつついざ死なむと思ふ
君が瞳(め)は海の流れてゐるごとく澄めりと云へば笑みたまひけり
生きよと如く河岸(かし)に真青き蓬生え死ねよと如く水流れけり
生きよと如く月のぼりけり河岸に来て真青き蓬摘んでゐるかな
草笛を涙に濡れて吹きにけり淡きおもひの胸に滲む日
己(おの)が病む如くに君は病みゐたり川は夜空を流れてゐたり
我は病みても君を忘れず君を恋はばまなうらに咲く幻の花
春の雪
春の雪花の如くに降る朝の狸小路にひとと別れぬ
春の雪花の如くにわがひとの髪にかかるはなやましきかな
君と逢ひ別れし町に花の散る如くに春の雪は降るかな
君がため
君がためただ君がため海に来てかもめの月に飜る見ゆ
君がためただ君がため月光に濡れて渚を歩み来しかな
君がため裏山行けり裏山に君好きたまふ秋草咲くに
君がため花摘みに来し裏山を星の光に濡れて下れる
藤咲けば
藤咲けば君の咲くやに思はるる思ひ出の山に一人登る日
東のかなた
陸橋に登りて東のかなた見ゆ東に君の住む町あれば
月の出
初恋の傷みに堪へて月の出を見てゐる大きな月出(い)でたれば
月の出を見てゐて瞼濡れにけり初こひびとは病みたまふらん
君が名をくちずさむ時幻の琴の音聞こゆ月の出の頃
青森
雪の日の胸の傷みに堪へかねて死なむと津軽海峡に来し
青森のをみなの呉れし青林檎食らひて海を渡りけるかな
月草の花
君に逢ひしその日海よりも轟くはわが胸に咲く月草の花
砂山に君と腹這ひ沖見れば白き破船の沈むこそ見ゆ
撫子
摘み摘みて胸に溢るる撫子を君に捧げむと来し野道かな
撫子の花が好きよと云ひしゆえ撫子摘みに野に出(い)でて来ぬ
日暮れまで野に居て君の香水の匂ひの花を捜してをりぬ
幻の花の香りが流れ来て君を思ひて名をくちずさむ
泣き濡れて浜撫子を摘みにけり病みても君を思ひけるかな
撫子を摘み摘み君は泣き濡れて夜空の星の如き涙す
君がためひとり撫子摘みをれば故なく涙流れ初めけり
ヒヤシンス
ヒヤシンス薄紫に咲きにけりはつかに星の瞬くに似て
ヒヤシンス夜空の星を映すかに心の庭に咲くは淋しき
ほの淡きヒヤシンスかな君が頬朝焼けいろに染まりしを見ゆ
北國の朝焼けいろの君が頬幼き君の遠き日のこと
汝(な)が瞳心の庭のヒヤシンス薄紫に咲けば悲しも
わが庭の薄紫のヒヤシンス君を思へば散り初めにけり
十三の君を忘れずヒヤシンスはつかに春の雪降る夕(ゆうべ)
汝(な)が頬はヒヤシンスよりやや薄く青ざめてゐる雪降ってゐる
波の音
わが胸に海の流れてゐるごとし恋はば胸より海鳥の発つ
わが胸に海流れをり君を恋はば胸より遠き波の音(ね)聞こゆ
淡雪
しらしらと朝降る雪を映すかに白かりしかの君が頬かな
てのひらにのりてはかなく淡雪は解け初むや君の命が如く
煙草吸ふとき冷たき涙流れけり北の都に病める人あり
君が文
君と見し海へ行かむと汽車にあり十三の日の君が文かな
君が声
北國の冬の終はりの夕空に響くが如き君が声かな
歯磨き粉の匂ひ
初恋の君と別れて来し日より歯磨き粉の匂ひして雪降ってゐる
歯磨き粉の匂ひして雪降ってゐる学校帰りの君の幻
歯磨き粉の匂ひして雪の降る朝(あした)君の幻美しきかな
シクラメン
シクラメンの花房見れば初恋の人去る如くさみしかりけり
花摘み
花摘みに来は来つれども花あらず出(い)で初めし星を摘みて帰りぬ
君が名
君が名を荒磯(ありそ)の岩が上に立ち汽笛の如く沖へ叫べり
君が名を星の出近き浜に出て流れ木に寄りて沖へ叫べり
初恋の傷み残れる君が名を荒磯の砂に書き遺しけり
砂に書く君が名消しゆく秋の波幾たび君が名を書きしかな
砂浜の砂に遺せし君が名は波に消されて幾秋経たむ
君が名を口ずさみつつ磯に来て真青き草を摘み渉るかな
君が名を千ほど砂に書きゐしが思ひはつきず月草を摘む
エルム
たそがれはエルムの山の淋しさに涙ぐみつつ君を思へり
郭公鳥
君へ文書きつつをれば夜は明けぬ郭公鳥など鳴き初めにけり
空知川
空知川の岸辺の町に君住むやそこはかとなき水の青さよ
平岸と云ふ空知の川の町に住む君を思へば雪降り初めぬ
雪に埋もれし空知川こそ悲しけれ飛ぶ鳥もなく釣る人もなく
空知川雪に埋もれて飛ぶ鳥もなければわが胸の如く淋しき
雪國
雪國に雪降る如くわが胸に君が涙の降りしきるかな
雪國に雪降る如くわが胸に君が面影棲むは淋しき
『西川徹郎青春歌集─十代作品集』(西川徹郎文學館叢書第1集/茜屋書店)は、2010(平成22)年西川徹郎作家生活50年を記念し文學館叢書第一集として刊行された西川徹郎の十代の日の短歌作品集。本集の「歯磨き粉の匂ひして雪降っている」は同歌集よりの抄出した170首である。同歌集には解説として斎藤冬海の「少女ポラリス」100枚が収載されている。

Ⅰ 初恋の少女
俳句の詩人西川徹郎の魂の原郷に聳えるのは、新城峠(しんじょうとうげ)である。西川徹郎は、新城峠の麓の浄土真宗本願寺派法性山正信寺に生まれ育った。新城峠は、北海道芦別市の北壁に位置し、西に向かえば音江連山の一つイルムケップ山、東に向かえば夕張山地から続くパンケホロナイ山という山々を東西に結ぶ尾根に当たる。山々は鬱蒼とした森林に覆われ、豊かな水脈を湛え、峠は美事な分水嶺を形成している。清らかな水が北へ南へと分かれて錚々と流れ落ち、峠の北側へ流れる水はやがて石狩川へ、南側へ流れる水は空知川へと注ぐ。新城の田畑を潤す泥川、新城川、新城六線川、七線沢などの幾筋もの流れは新城市街を横切って、パンケホロナイ川に出会い、やがて空知川に合流する。
西川徹郎の第一句集『無灯艦隊』(1974年)は、新城峠より見晴るかす、扇のように打ち重なる緑の丘陵の光景を深い海原に喩え、「青春の日の叛意と新たなる出立と俳句革命の意志を表し」(エッセイ「新城峠」、「抒情文芸」2007年春号)て命名された。『無灯艦隊』に搭載された俳句作品は、西川徹郎の青少年期に当たる1963年から73年の10年間に日夜書き継がれた凡そ七万句余りの中から選ばれた220句である。現在当時の数十冊に及ぶ創作ノートが旭川西川徹郎文學館に収蔵保管されており、現在までに『東雲抄』(『西川徹郎全句集』所収、2000年・沖積舎)として2000句が、『幻想詩篇 天使の悪夢九千句』(編者註・2013年6月刊)として9000句が発表されている。
西川徹郎は十代の日より現在までに凡そ十五万句に及ぶ膨大な俳句作品を書き続けてきたのである。それらを収めた創作ノートの中には俳句と同時に、窃かに短歌も詠まれ遺されていた。短歌作品が詠まれたのは、西川徹郎の北海道立芦別高等学校在学中の15歳から、京都・龍谷大学文学部国文学科を自主退学して帰郷した20歳になる頃までの、10代の僅かな期間のみである。しかし俳句も短歌も共に新城峠の分水嶺から分かれ落ちる水脈のように、もとは少年詩人の崇高な詩魂から溢れ出た清冽な潺(せせらぎ)に他ならない。
短歌作品は、計97首が1965年から66年にかけて芦別高校文芸部発行の「シリンクス」に発表された。また同時期「北海道新聞」歌壇に投稿した2首が小田観螢の選により紙上に掲載された。これらの西川徹郎の短歌に就いては、石狩市在住の歌人・文芸評論家高橋愁(1942年~)が一千枚の書き下ろし評論『暮色の定型―西川徹郎論』(1993年・沖積舎)の中の「短歌編」章にて論じている。同書には、西川徹郎が「シリンクス」に発表した短歌全てが発表当時の形で収載されており、「北海道新聞」の「道新歌壇」入選作品2首も提示されている。本書には、それら既発表の作品を含め、全41章384首を収める。
西川徹郎の短歌作品は、殆どがある一人の少女に捧げられた恋の歌である。一体どのような物語が秘められているのか。芦別市新城町の市街地で呉服店を営んでいた蓑輪商店の長女曽我部芳子(旧姓蓑輪、赤平市在住)は、西川徹郎が通った芦別市立新城小中学校の同級生で、現在西川徹郎文學顕彰委員会・西川徹郎文學館友の会「星雲の会」会員でもあり、西川文学の応援者だ。曽我部芳子が語った西川徹郎少年の初恋の物語によれば、中学一年時に転校してきた桑野郁子という少女がいた。新城の営林署(芦別支所新城駐在所)に転勤となった父親に伴って札幌からやって来たのだ。この少女は西川少年の中学一年の二学期の初め頃に新城中学校に転入し、二年時の二学期の終わりの初雪の降る頃に他校へ転校したと考えられる。桑野郁子は、新城の田舎育ちの子供とは全然違う都会的な雰囲気の清楚な可憐な少女で一躍クラスの注目を集めた。正信寺に隣り合う新城神社の丘からは、桑野郁子の住む営林署の官舎の屋根を臨むことが出来たので、西川少年は憧れの少女を偲んで寺の裏山伝いに神社の丘に登るのが常となった。
白鷺の城のごとくにあるゆえに秋草に寝て君を思はむ (君が家)
君が家見むとて丘を登りつつ撫子摘めば腕に溢れぬ (〃)
しかし次の年には父親が隣の町の赤平市に転勤となったために再び転校して行ってしまった。営林署の官舎は正信寺からほど近い江村沢川の川縁にあり、川の向かいには加藤鉄工所があって同級生の加藤拓栄子(現在、旭川市在住)が住んでいた。曽我部芳子が加藤拓栄子から聞いたことには、夕暮れ時になると自転車に乗った西川少年が江村沢川に架かる江村沢橋のたもとにやって来て、既に桑野郁子の去った後の家屋を暗くなるまで見つめているのを何度か目撃したというのである。
君が手に初めて触れし秋の夜の木橋に涙ぐみつつ佇(た)てり (病みたまふ君)
秋風に荒家と化せし君が家夜毎に犬の遠吠える家 (君が家)
赤平市平岸町の街外れ君住むといふ灯の点る家 (空知川)
空知川の岸辺の町に君住むやそこはかとなき水の青さよ (〃)
更に後年、曽我部芳子が西川徹郎から直接聞いた話によると、芦別高校入学後、間もなくのこと、もう会えないものと思っていた桑野郁子の姿を思いがけず芦別高校の校舎の中で見た。桑野郁子は父親が赤平市から再び芦別市東頼城の営林署に転勤となり、芦別高校に通うようになっていたのだ。西川少年は驚き、その再会を運命的な出会いと感じたという。
陸橋に登りて東のかなた見ゆ東に君の住む町あれば (東のかなた)
だが又しても少女は姿を消す。西川少年は職員室を訪ね、担任の教師から桑野郁子が芦別市内の病院に入院したことを聞き出す。胸を痛めつつ病院へ向かうが桑野郁子の姿はなく、看護婦に問い尋ねて、その少女は脊椎カリエスという不治の病で、治療のため札幌市の病院へ転院したと告げられる。愕然としながら西川少年は札幌市の月寒高校に転校したという情報をもとに桑野郁子を尋ねて札幌に赴き、一人冬の月寒の町を彷徨い歩いた。
君を語る看護婦の瞳(め)にそこはかとなく凍りたる湖(うみ)の浮べり(病みたまふ君)
冬来れば月寒町の裏通り哀しき歌を唄ひ歩めり (月寒町よ)
月寒町のバスストップのかなしけれ冬日に影となりつつ立つは (〃)
たそがれは見知らぬ町をさまよひてたどりつきたる冬の停車場 (〃)
高校卒業後、京都の龍谷大学に進学したものの、二年で自主退学を決意した西川徹郎は、晩秋の故郷に帰る。在学中、京都にては『酒ほがひ』『祇園歌集』等が収録された吉井勇(1886~1960年)の岩波文庫『吉井勇歌集』などを手に彷徨し、賀茂川、祇園、歌舞練場、東山、清水、鳥辺野などを舞台にした作品を多く書くが、心は常に初恋の少女にあった。
わが身病む如くに君は病みゐたり川は夜空を流れてゐたり (幻の花)
煙草吸ふとき冷たき涙流れけり北の都に病める人あり (淡雪)
遙かなる比叡の鐘を数えつつ人の恋しき夜となりにけり (賀茂川)
帰郷した西川徹郎は桑野郁子の父親が営林署に勤務していることを手掛かりにして、ようやく1968年の春3月、札幌市の簾舞という町に少女の家を探し当てた。ついに相見えることの出来た桑野郁子自身の口から、脊椎カリエスは誤診であったことを聞かされて胸を撫で下ろし、ただ一回のみのデートを約束して、徹郎は少女の家を後にした。中学時代に芽生え、二十歳となるまで思慕し続けた少女への初恋は成就せず竟る。
月の出を待つが如くに君を待つ君影の花匂ふ喫茶店 (幻の花)
わが前に幻として君は在り幻の花匂ふ喫茶店 (〃)
白藤の花が匂ふと囁かば頷きたまふ君なりしかな (〃)
君が髪梳けばさやけき藤の香の町に匂ふとわれ囁きぬ (〃)
君に逢ひ別れて来れば白藤の匂ひの髪に滲みてありけり (〃)
月見草野に咲く如く我もまた一人野に出て君を思はむ (〃)
月見草咲く野に出(い)でてひと思ふこの淋しさを誰に語らむ (〃)
何処となく笛の音聞こゆ初恋のひと吹くらむか花蔭にして (〃)
蒼白くをみな子薄き星に照りはにかんでをり草編みながら (〃)
我は病みても君を忘れず君を恋はばまなうらに咲く幻の花 (〃)
春の雪花の如くに降る朝の狸小路にひとと別れぬ (春の雪)
君と逢ひ別れし町に花の散る如くに春の雪は降るかな (〃)
青ざめし心の如きあおき花狸小路にふってゐるかな (〃)
ひと恋へば心のなかの薄野を暗き笛吹き渡る人あり (〃)
孤独な少年詩人の凡そ八年間にも及ぶ恋の年代記は、花のように淡雪の降り注ぐ永遠の時間として短歌作品の中に封じ込められた。それ以後西川徹郎は一首たりと短歌を詠むことはなかった。それは一人の少年詩人の、短歌形式に捧げた魂の夭折ともいえるだろう。ひっそりと創作ノートの中に眠っていた短歌作品を、この度西川徹郎作家生活五十年記念出版、西川徹郎文學館叢書の第一集として刊行する。〈世界文学としての俳句〉を提唱し、実存俳句を書き続ける西川徹郎の文学の歴史の中に在って夭折した少年歌人の作品も又、日本文学史上に類い希な詩精神の香気と文学の光芒を放ち、西川徹郎の文学世界を荘厳しているのである。
わが胸に海の流れてゐるごとし恋はば胸より海鳥の発つ (幻の花)
しらしらと朝降る雪を映すかに白かりしかの君が頬かな (淡雪)
君が名を荒磯の岩が上に立ち汽笛の如く沖へ叫べり (君が名)
Ⅱ 詩の溶鉱炉
連山の凍り横たふそのもとに溶鉱炉静かに火を吐きてをり (秋の町)
日々新城峠が見せてくれる光景の中でも特筆すべきものは夕映えの素晴らしさである。地球の地軸の傾きが関係するのか、未だイルムケップ山の頂に残雪が光る四月の半ば頃と、晩秋に入らんとする九月の終わり頃には殊に天の業火と喩えたいほどの夕焼けが見られる。日が落ちたばかりのイルムケップの山頂は音を立てて白く煮え滾り、周囲の空を紅蓮に染め上げる。西川徹郎文學館三階展示室の新城峠の夕映えのパネル写真を見て「これは夕焼けじゃない、火事だ!」と叫んだ来館者もいる。西川徹郎は、日本海に落ちる夕陽がイルムケップ山に照り映えるため、凄まじい夕焼けになるのだと言う。西の山の遙か彼方には、西川徹郎が殊に好んで今でも年に数度は車を駆って見にゆく、インドのマドラス、スコットランドのウィックと並んで世界の三大波濤に数えられる留萌・増毛の荒涼とした海流がある。
掲出歌にある凍れる山の麓の溶鉱炉とは、例えばこの夕焼けのことではないかと思わせられる。燃え盛る火の前には、恋人の睫毛にそっと訪れるような淡雪や春の雪はひとたまりもない。西川徹郎は、詩の溶鉱炉に自らの詩心を投げ込み、鍛え上げた。その結果が、西川徹郎26歳の年に刊行された第一句集『無灯艦隊』(1974年)である。西川徹郎を劇的な恋愛歌人にした抒情の翼は焼き切られ、手には俳句という輝く鋼の刃(やいば)が握り締められたのである。
ここで西川徹郎が少年の日に触れた作家や文学作品等を『西川徹郎全句集』(2000年・沖積舎)他の年譜から辿ってみたい。小学校の二年生頃まで病弱だった徹郎少年は、自宅で療養中に、枕元の屏風に祖父であり正信寺開基住職で当時北海道を代表する本願寺派布教使、勤式・声明の指導者であった西川證信(1888~1963年)の手で毛筆で書かれた芭蕉や一茶の発句、『教行信証』の「正信念佛偈」や「信巻」十二嘆名の釈文を、目に当て心に刻み込んだ。これらが後に西川徹郎の文学精神を支え、又、真宗学者西川徹真の宗教的信念を支える言葉となった。同時に、発句の持つ五七五や偈文の持つリズム、漢詩や経典等から汲み上げた豊かな文学的素養を持つ親鸞(1173~1262年)の著作の雄渾にして流麗な筆致も又、西川文学に大きな影響を与えたと言えるだろう。
又、小学校の修学旅行で初めて札幌市に行った折、自由行動の時間に、母方の叔父神埜努(つとめ)(1924~2017)が勤務していた北海道新聞社を訪ね、叔父より「イソップ物語」の単行本を貰ったが、これが初めて手にする自分の本であり嬉しかったという。因みに神埜努は同社の政治経済部、学芸部の記者をしていたが、郷土史や有島武郎(1878~1923年)・宇野千代(1897~1996年)等の研究家でもあり、『女流作家の誕生―宇野千代の札幌時代』(2000年・共同文化社)等数冊の著書を持つ。学芸部在任中は、北海道新聞社が招待した瀬戸内晴美(寂聴)の講演・取材旅行の案内役として同行したり、有島武郎の「生まれ出づる悩み」(1918年)のモデルとなった岩内出身の画家木田金次郎(1893~1962年)と親交を結んだりしている。瀬戸内晴美の新聞連載小説『妻たち』(新潮文庫)には、努夫妻をモデルにした夫婦も登場している。努は学芸部勤務の時、女性の投稿欄「いずみ」を創設し、この欄は現在も同紙にあって読者に親しまれている。徹郎の母貞子(1920~99年)の弟で、神埜家は北海道空知郡南幌町にある浄土真宗本願寺派妙華寺の住職の家系。
祖先に歴史的真宗学者で、江戸時代の本願寺派第六世能化實明院功存(享保5~寛政8年、1720~1796年)がいる。
芦別高校に入学した西川徹郎は文芸部と図書館部に入部、書庫にも自由に出入りして、北條民雄・芥川龍之介・萩原朔太郎・大手拓次・宮沢賢治・石川啄木・斎藤茂吉・吉井勇などの文芸書や、特に当時目にして感動した関根正三やシュルレアリスム関係の絵画集、ダリの芸術論などに惹かれて読み込み、筑摩書房『日本文学全集』中、「現代俳句集」に収録されていた種田山頭火・尾崎放哉・高柳重信・富澤赤黄男・西東三鬼・細谷源二らを耽読した。日本文学のみならずダンテ・ボードレール・アポリネール・ランボー・ロートレアモン・プルースト・ドストエフスキー・トルストイなどこの時期に目にした古今東西の文学作品や絵画集が、西川文学の糧となり、また世界文学としての西川文学を鍛えるものとなった。本格的に俳句を書き始め、西川俳句の文学世界はまさに〈無灯艦隊〉として姿を顕し始めていた。
それにしても、「溶鉱炉」の一首だけを見てもこれが十代の少年の手による作品とは到底思えない。端正でありながらイメージの喚起力が圧倒的であり、何よりも戦慄させられるのはその読み手の脳裏に描き出される一首の世界が、日常的スケッチの凡庸を離れ、氷の世界で永遠に点り続ける火を見つめているかのような森閑とした深みを湛えていることだ。連山が凍る、連山が横たふ、と時間と空間を一気に把握し、溶鉱炉という激しい対象物を一旦「静かに」と鎮め、次に「火を吐く」と動に戻す自在なレトリックを既にこの少年は易々と行っている。
因みに本書に収載された短歌が詠まれたのと同時期に書かれた俳句を、『無灯艦隊』と『東雲抄』(『西川徹郎全句集』所収、2000年)から挙げてみよう。
不眠症に落葉が魚になっている (『無灯艦隊』)
海峡がてのひらに充ち髪梳く青年 (〃)
剃刀研ぎと冷やされし馬擦れちがう (〃)
癌の隣家の猫美しい秋である (〃)
京都の橋は肋骨よりもそり返る (〃)
京都の鐘はいつしか母の悲鳴である (〃)
晩鐘はわが慟哭に消されけり (〃)
男根担ぎ佛壇峠越えにけり (〃)
北国は死者の口笛止む間無し (『東雲抄』1963~73年作)
凍る町の少年の日の金属音 (〃)
群れを離れた鶴の泪(なみだ)が雪となる (〃)
こんなきれいな傘をはじめてみた祇園 (〃)
病院裏の飯粒よりも小さな白馬 (〃)
屠馬は七夜一睡もせず星数え (〃)
Ⅲ 西川徹郎と石川啄木
勿論、短歌にせよ俳句にせよ他の詩人たちと同様に、少年詩人西川徹郎にも習作期があった。西川徹郎が初めて俳句を書いたのが小学六年生の冬休みだという。宿題のために二十句ほど書き上げ提出したところ、その早熟振りを教師に驚かれ、不審の眼を注がれた。
又、初めて短歌を詠んだのは中学二年の国語の授業でのことであった。教師に短歌を作れと言われ、三、四首詠んだところ「西川君の作品は、専門にやっている大人の歌人でも書けん」と褒められ、読み上げられた。生家正信寺の経蔵にあった石川啄木(1886~1912年)の詩集『あこがれ』(1905年)や歌集『一握の砂』(1910年)を読み耽り、詩歌に目覚めた西川少年は、俳句や短歌の創作にのめり込んでいった。残念ながら現存はしていないが、授業中にノートや教科書の端に多くの俳句や短歌の詩句を書き続けたのであった。
このような小中学時代の習作期を経て、高校時代は西川翠雨というペンネームを用い、文芸部の雑誌「シリンクス」に俳句や短歌を発表し、北海道新聞の俳壇欄の細谷源二(1906~70年)選や土岐錬太郎(1920~77年)選に投句し、細谷源二主宰の「氷原帯」に俳句作品を発表した。校内誌や新聞に作品が掲載されて、西川翠雨が西川少年のペンネームであることが知られ、級友たちからは「スイウ、スイウ」と呼ばれて持て囃されたという。
当時のペンネームとして使用された「翠雨」とは、石川啄木が16歳の時用いた「翠江」の号と、啄木の函館時代の友人宮崎郁雨の名から取ったもので、西川徹郎の青春期の啄木への傾倒が見て取れる。因みに啄木が宮崎郁雨の名を読み込んだ作品が
大川の水の面を見るごとに
郁雨よ
君の悩みを思ふ (『一握の砂』)
であり、
智恵とその深き慈悲とを
もちあぐみ
為すこともなく友は遊べり (同)
は郁雨を詠んだものという(『定本石川啄木歌集』岩城之徳編・解説、學燈社)。既存の美意識に依るのではない新しい短歌表現を志し、苦悩しつつ歩む人間の姿を率直に詠む啄木の作品は当時から注目されていたが、西川少年の心をも又捉えた。
「一握の砂」という歌集のタイトルにもなった言葉は、佛弟子の佛法僧の三寶への敬信を表す「三帰依文」を想起させる。それは「人身受け難し、今已に受く、佛法聞き難し、今已に聞く」と始まる文である。釈迦がガンジス河の辺で河原の無尽の砂から一握りの砂を掬い取って弟子の阿難に示し、生きとし生くるものの中で人間に生まれる者はこの一握の砂ほど稀であることを伝え、更にその中から指先で砂を摘み、佛法に遇う者は指先の砂ほど僅かであると説いたことによる。釈迦の示した「一握の砂」とは苦悩の人間存在そのものであり、岩手県日戸村の曹洞宗常光寺に生まれ、渋民村宝徳寺で育った啄木も恐らくは「一握の砂」という言葉に、人間に生まれたということ、人間存在の意味への問いを短歌表現において追究していくという志を籠めたのであろうと思われる。
西川少年はその後、新興俳句の旗手の一人細谷源二が主宰し、当時俳壇で全国的に注目されていた俳句誌「氷原帯」の新人賞を受賞し、細谷源二や星野一郎(1926~2009年)、評論家中村還一(1898~1976年)等から天才詩人と絶賛されて高校生俳人として文学の世界にデビューする。その折りに当時の本名であった西川徹郎を名乗り、寺門継承の為に西本願寺で得度し法名釈徹真を授かった後は、徹真を本名とし、徹郎を筆名としている。
啄木の哀しみをもて飯食へば流るる涙の冷たくもあり (秋の町)
秋近き神社の森で拾ひたる白き電球を点けてみるかな (〃)
大いなる瞳を持てる君こそは雨の中なる馬鈴薯の花 (馬鈴薯の花)
啄木の恋の歌よりわが詠ふ歌かなしけれ馬鈴薯の花 (〃)
裏山に桐の青葉のさやぐなりわが青春を育みし家 (〃)
少年の淋しく揚ぐる凧の如き恋初めし日の秋風のわれ (〃)
桐の葉に頬を埋めて初恋の後の傷みに堪ふるものかな (〃)
砂山に君と腹這ひ沖見れば白き破船の沈むこそ見ゆ (月草の花)
君を思ふ夕べ砂山月草のはらはらと散るを怖れつつ見き (〃)
君が手を取りて荒磯(ありそ)を渉りつつ海より深きあはれを思ふ (〃)
摘み摘みて胸に溢るる撫子を君に捧げむと来し野道かな (撫子)
別れなる朝に贈りしわが庭の花はかの花君影の花 (別れなる朝)
五年前の君が腕(かいな)と我が腕いとか細くもありしものかな (病みたまふ君)
三日月の微光に濡れし君が頬半跏思惟の君なりしかな (旅人)
水匂ふ朝は雪降り初めにけり二十歳になりしひとを思へる (口笛)
紫の野花の茎を噛みにけり初こひびとは病みたまひつつ (野花)
青白き梨の蕾に降る雨の如くに涙流しひと恋ふ (〃)
初恋の傷み残れる君が名を荒磯の砂に書き残しけり (君が名)
砂浜の砂に残せし君が名は波に消されて幾秋経たむ (〃)
藤咲けば君の咲くやに思はるる思い出の山に一人登る日 (藤咲けば)
十三の君を忘れずヒヤシンスはつかに春の雪降る夕(ゆうべ) (ヒヤシンス)
雪國に雪降る如くわが胸に君が面影棲むは寂しき (雪國)
石川啄木の短歌作品には、明らかに西川少年が意識している次のような作品がある。
愁ひ来て
丘にのぼれば
名も知らぬ鳥啄めり赤き茨(ばら)の実 (『一握の砂』以下同)
ふるさとの空遠みかも
高き屋にひとりのぼりて
愁ひて下る
馬鈴薯のうす紫の花に降る
雨を思へり
都の雨に
馬鈴薯の花咲く頃と
なれりけり
君もこの花を好きたまふらむ
砂山の砂に腹這ひ
初恋の
いたみを遠く思ひ出づる日
ゆゑもなく海が見たくて
海に来ぬ
こころ傷みてたへがたき日に
うす紅く雪に流れて
入日影
曠野の汽車の窓を照せり
ひと夜さに嵐来たりて築きたる
この砂山は
何の墓ぞも
空知川雪に埋れて
鳥も見えず
岸辺の林に人ひとりゐき
西川少年が通う芦別高校への通学バスは、朝夕必ず木々に縁取られた美しい空知川を渡る。空知川はいわば西川少年のテリトリーにある。
雪に埋もれし空知川こそ悲しけれ飛ぶ鳥もなく釣る人もなく (空知川)
空知川雪に埋もれて飛ぶ鳥もなければわが胸の如く淋しき (〃)
これらの啄木に応答するかのような作品があるが、啄木が旅吟であることに対し、西川少年が生活や存在と一体となった空知川を主題としているところに、悲哀は啄木の叙景歌を超えて高まる。ここに日本歌壇の代表作家石川啄木への敬意を込めた密かな挑戦を見て取ることが出来る。
わが胸に黒き小旗の烈風に靡くが如く心荒れをり (宿命)
には中原中也(1907~37年)の「曇天」(『在りし日の歌』)の、
ある朝 僕は 空の 中に、
黒い 旗が はためくを 見た。
はたはた それは はためいて ゐたが、
音は きこえぬ 高きが ゆゑに。
と始まる詩を思う。西川徹郎には俳句作品として、短歌と同じ「黒い旗」を書いた、
念佛や夜闇に黒い旗靡く (1973年・『東雲抄』)
という句があるが、中也の描いた網膜に焼き付くような、身を絞る祈りのような虚空に激しくはためく旗とは逆に、西川徹郎の旗は闇夜の中の黒い旗であり目には見えない。ただ音として聞こえるのであるが、その音とは、『佛説無量寿経』に十方に響流して究竟して聞こえない所は無いと説かれる大いなる絶対者(如来)の呼び声なのである。
赤平の文京町に雪降れりわが胸底に降るがごとくに (宿命)
雪國に雪降る如くわが胸に君が涙の降りしきるかな (雪國)
に、ヴェルレーヌの
都に雨の降るごとく/わが心にも涙ふる。―― (「都に雨の降るごとく」鈴木信太郎訳)
を思い浮かべるのであるが、西川少年は「文京町に雪の降るごとく」とは言わず、雪は彼の「胸底に降るがごとくに」降る。又、「雪國に雪降る如くわが胸に」降りしきるのは、わが涙ではなく「君が涙」である。抒情的な風情とはうらはらに、定型のリズムに乗せた流暢な一首の中に、冷徹と言ってもよいほどひねりを効かせた巧みなレトリックが駆使されている。
犬橇の柩のなかに凝固せる己が額に雪の積もれり (宿命)
には彼もまた十四歳から和歌を詠み始め、二十八歳で暗殺によりその生涯を閉じた鎌倉幕府三代将軍、右大臣源実朝(1192~1219年)の、
われのみぞ悲しと思ふ浪のよる山のひたひに雪のふれれば 源実朝 (齋藤茂吉校訂『金槐和歌集』)
を思わせられたが、ヴェルレーヌに対し「赤平の文京町」を突き付けたのと同様、未だ見ない老いの哀しみを透明な調べで詠う実朝に対しては「犬橇の柩」で野辺に送られる、雪の野に生き死ぬ自己を凜烈なイメージを以て提示する。
鳥辺野に恋に破れて泣きに来し大工の紺の瞳を思ふ (鳥辺野)
に於いては若い大工が登場する。西川徹郎の描く「大工」はどこかで庶民を逸脱する存在だ。大工は慎ましい生活者としての庶民の代表でもあるが、例え貧しい一青年であったとしても彼が卓抜した技芸を持つ者である時、永遠を求めて何ものかを建立しようとする勇猛な志ある者というイメージを持つ。日本に佛法を広め、法隆寺を建立した聖徳太子が大工を守護する菩薩として崇められ、現代においても建築関係者が聖徳太子祭を執り行ったりしていることや、イエスの父が大工ヨセフであったこと、太宰治の「花きちがひの大工がゐる。邪魔だ」(「葉」『晩年』所収)という警句めいた一句などが思い浮かぶ。因みに西川少年の生まれ育った正信寺においても、長らく境内の聖徳太子堂に於いて、新城町の住民によって上宮太子奉賛法要が修行されてきた。抑も新城町は樵(きこり)が伐り拓いた村と言われ、豊かな山林を有する木材の産地であった(『新城町百年史』)。故に桑野郁子の父親が勤務した営林署の支所が帝室林野局の新城駐在所として設けられた1933年から1994年(名称は92年より「新城森林事務所」)まで置かれており、住民にも大工をする者が多かったのである。正信寺の太子堂には、大工道具である曲り尺を手にした可憐な少年の姿の聖徳太子像が安置されている。
斎藤茂吉(1882~1953年)の『赤光』(1913年)にある一首、
めん鶏(どり)ら砂あび居たれひつそりと剃刀研人(かみそりとぎ)は過ぎ行きにけり 茂吉
に描かれためん鶏らと剃刀研人との緊張を孕んだ真昼の邂逅は、ナイフのような影を連れて歩む「剃刀研人(かみそりとぎ)」のイメージと共に一読忘れられないシーンである。この一首は独立した一首として充分不穏な状況を伝えるが、次の、
たたかひは上海に起り居たりけり鳳仙花紅く散りゐたりけり 茂吉
という一首とともに「七月二十三日」という小題で括られている。歌集刊行の翌1914年、第一次世界大戦勃発。一方西川徹郎の短歌においては、
星の出に剃刀研人(かみそりとぎ)は月見草摘み摘み深き裏山行けり (剃刀研人)
と、場面は星の出た夜となる。剃刀研人は花を摘みながら裏山の奥深くを歩んでいる。「月見草」と「摘み摘み…」と韻を踏みつつ「罪深き」という音が導き出される。裏山を急ぐ剃刀研人を追った一連の作品には剃刀研人を剃刀研人たらしめる内面の異様な緊張が描かれる。西川徹郎の短歌には同時期に膨大な量が書かれていた俳句表現に隣接すると感じられる作品があり、剃刀研人(かみそりとぎ)も西川徹郎の俳句に登場する。
剃刀研ぎと冷やされし馬擦れちがう (『無灯艦隊』)
「冷やされし馬」は西川少年が20歳となる頃まで新城町にも飼っている農家があった農耕馬のことであり、西川少年は実際に、厳しい真夏の農作業を終え、夕闇が迫る川で洗われて、熱くなった体を冷やされている馬を見たことがあったという(エッセイ「夏の日」「銀河系通信」第19号所収、2006年)。同句は、「海程」一九六九年六月号に発表された「尼寺」九十三句の中の一句である。
歌人塚本邦雄(1920~2005年)に、
馬を洗はば馬のたましひ冱ゆるまで人恋はば人あやむるこころ 邦雄 (『感幻楽』1969年)
という作品があるが、耽美を極めようとする塚本邦雄の描く馬とは逆に、西川徹郎の描く馬は、常に人間の側にあって大きな瞳に人間の生を映し、人間の生の悲哀を曳いている。
父よ馬よ月に睫毛が生えている (『無灯艦隊』)
馬の瞳の中の遠火事を消しにゆく (〃)
暗い地方の立ち寝の馬は脚から氷る (〃)
ねむれぬから隣家の馬をなぐりに行く (第二句集『瞳孔祭』1980年)
蹄鉄屋より胎児ころがる夕月夜 (〃)
農耕馬は、春夏秋と田畑で働き、冬は深い雪の中で馬橇を曳いて人や荷物を運搬する、農村の人々の生活になくてはならない存在だった。又、村から村へ刃物を研いで廻る刃物研ぎ師もその時代にいた。包丁は砥石で研いだが、剃刀は肩から掛けた幅広い革のベルトに刃を滑らせて研いだ。この剃刀を研ぐ革が馬革だった。「冷やされし馬」と「剃刀研ぎ」の擦過は、死と生との極限に達し、一瞬の青白い光を放つ。西川徹郎は、日本経済が高度成長期に入る寸前、馬が人と共に暮らしていた最期の時代の記憶を持つ世代だ。その時代の闇黒と生きるものの息遣いまでもが感じられる情景を、西川徹郎の俳句は見事に映し出す。
更に西川少年の短歌を掲げてみよう。
藤咲けば君が咲くやに思はるる思い出の山に一人登る日 (藤咲けば)
薄紫の藤の花は決して地味な花ではない。庭の藤棚に行儀良く下がっている藤の花房でさえ豪奢で、遠く離れていても強く薫ってそれと気付く。まして聳える山の木々に巻き付き、森林の最も高い場所まで巻き登り、空高く陽を浴びながら一斉に咲き誇っている藤の花には圧倒的な生命力が感じられる。「君が咲くやに思はるる」と、古代の日本神話の大山祇神(おおやまつみのかみ)の娘、邇邇藝命(ににぎのみこと)の后である「木花之開耶姫(このはなのさくやひめ)」をイメージさせつつ、青春の日の生命力の輝きが、読む者の心を照らし返すような一首である。
初恋の傷みに堪えて月の出を見てゐる大きな月出(い)でたれば (月の出)
君が名をくちづさむ時幻の琴の音聞こゆ月の出の頃 (〃)
何一つ遮るものの無い月の航路である。新城峠の峡谷の月夜の景色の素晴らしさは譬えようもない。イルムケップ山に日が落ちる頃、黎明舎(正信寺)の裏山の新城神社の森の奥から、まだ明るい東の空に白い大きな月が昇る。暮れて行くに従って月は輝きを増し、一晩懸けて西へと向かう。やがて朝焼けが西の空まで染める頃、ひっそりと貝殻のような白い月が、西の山の上にまだ浮かんでいたりするのである。黎明舎には「月愛の間」や「月の間」という名が付いた客室があり、一晩中月を眺めていることが出来るが、客人は時として余りの月明かりで眠れない。『竹取物語』の昔から人間の愛の物語は数限りなくあるが、西川少年の思う人は一人である。「大きな月」によって一層に切なさが迫る。
君が死の夢を見し日に裏山の藤の花のみ散り初めにけり (病みたまふ君)
に於いては、夢にも現(うつつ)にも恋人の死の予兆に震える少年の不安な心を詠む。「死」と「藤」=「不死」との取り合わせ、サ行の繰り返し、イ音の韻の配置の妙に驚かされる。
月の出を待つが如くに君を待つ君影の花匂ふ喫茶店 (幻の花)
に於いては、恋人は澄んだ月影であり、可憐な花である。読む者は空高く月の辺に飛翔し、喫茶店の卓の花の前に舞い戻る。天空に輝く月球が、そのまま君影の花=鈴蘭の花の小さく灯る鈴となり、〈君〉への思いが結実する。月影は君影と変奏され、〈君影の花〉となり〈幻の花〉となる。イメージの喚起力に加え、「月の出」の「ツ」の韻が「待ツ」「君を待ツ」と漣のように繰り返され、「月」の「キ」によって「君を」「君影の花匂ふ」「喫茶店」と韻を踏むようにたたみ掛けられ、更にカ行の音が「月」「待つがごとく」「君」「君影」「喫茶店」と連続し、喫茶店で恋人を待つ初めてのデートで、次第に高まって行く想い、更にそれを抑制しようとする心の動きまでが見事な臨場感とリアリティを獲得して表現されている。大空にまで広げた視野を、瞬時に目前の小さな花に絞り込む圧倒的なイメージの再現性と韻律の魔術を駆使した作品が、畏るべきことに十代の少年によって詠まれたのである。「幻の花」章は、本書のクライマックスであると同時に、少年詩人西川徹郎の青春のクライマックスでもあった。
我は病みても君を忘れず君を恋はばまなうらに咲く幻の花 (幻の花)
「幻の花」章は、思慕し続けた少女と遂に会うことが出来たただ一回のみのデートを詠った章である。目の前の少女はやはり幻の花であった。徹郎少年の現実生活に於いては、大学を中退して帰郷したものの生家の父は体調が思わしくなく、床に就いていた。そのため父に代わり僧籍を持たぬまま父の僧衣を着けて、雪の降る日も風の吹く日も、新城峠の寒村の門徒の家々を読経して廻った(『無灯艦隊ノート』1997年)。家業を支えなければならない重圧に、自身の失恋の傷手も加わった状態にあった。この一首の如く七七六七七という破調を以てしか表現することの出来ない心の呻きを抱えながら、少年は詩作というナイフを握り締め、彷徨を続けていた。
君がためただ君がためわが心枯野の如くなりにけるかな (君がため)
後年西川徹郎は、自らの俳句思想を「反季・反定型・反結社主義」と明確に述べ、〈世界文学としての俳句〉を提唱し、実存俳句を書き続けるが、破調について、松尾芭蕉(1644年~94年)の発句、
旅に病で夢は枯野をかけ廻る 芭蕉
を引いて次のように述べている。
「上五の「旅に病で」は、(略)明らかに「旅ニ病ンデ」と口語による破調表現が為されているのである。この「病ンデ」と一字はみ出した口語表現の中に、俳聖松尾芭蕉の、あくまでも独りの生活者としての実存が垣間見える。これは芭蕉の辞世の絶句である。この芭蕉辞世の絶句の一字はみ出した言語の中に、芭蕉五十一年の生涯の思惟の総てが呑み込まれているのである。(略)「病ンデ」の一字はみ出した口語が、芭蕉をして実存の未知の荒野へと歩み出させる一歩を確実に書き止め得たのである。」(「反俳句の視座―実存俳句を書く」「國文學」7月号、2001年・學燈社)
西川少年の短歌は基本的に歴史的仮名遣いによる文語表記で書かれたが、「我は病みても君を忘れず」の一首は失恋による大きな心身の喪失感により、殆ど口語の破調表記と隣り合わせの表現が為されていると言っていいだろう。更に2005年、第五十回口語俳句全国大会(口語俳句協会主催、静岡県島田市)の記念講演「口語で書く俳句―実存俳句の思想」に於いて、西川徹郎は松尾芭蕉の同作品を引き、
「わが身に至らんとする漆黒の死の闇を予感しつつ、その末期の床の中で為した起死回生の口語による無季・非定型の一句が、この辞世の句なのであります。ここには、付句や連衆等の一切の俳諧連歌の共同性を断ち切って、あくまで一句独立した未曾有の銀河系が成就しているのです。/この芭蕉の辞世の一句こそ、わが国の文学史に於いて、口語で書かれた俳句の嚆矢(こうし)であり、それはまさしく俳聖松尾芭蕉に於ける「実存俳句宣言」であったと私は思います。/ここに確かに枯野に遺され見捨てられてきた儘の、荒野の中の一本の道があります。この道は、明治期に在って、あの正岡子規が踏み損ねた道なのであります。/日は暮 れて既に暗いが、この荒野の中に遺された一本の道を、私は遙かに三百余年の時空を超えてここに継承し、唯ひたすらに口語による反季・反定型の実存俳句の隘路を歩み抜いて行く覚悟をあらたにするものであります」 (「銀河系通信」第19号所収、2006年・黎明舎/茜屋書店)と述べて、松尾芭蕉を遙かなる先達として、〈世界文学〉へ連らなる俳句興業の正統の道を自らも歩んでいくことを宣言したのだった。
君と逢ひ別れし町に花の散る如くに春の雪は降るかな (春の雪)
西川徹郎はこの短歌作品において、ハ行の「花」「春」「降る」を重ねて柔らかな情感を醸し出し、別れの悲しみを「散る花」、「降る雪」と共に永遠の時間の中に封じ込めた。二十歳となった西川徹郎は、その後短歌を書くことは無かった。ここに少年の心の荒野は、その後俳句の詩人西川徹郎が切り拓く豊穣な俳句文学の沃野となるのである。
以上の如く、石川啄木を始め主に日本文学史上の代表的詩人や歌人等の作品との比較検証を進めて来た。限られた紙幅の中の検証ではあるが、それでも西川徹郎の十代作品が、彼らの代表的な作品と肩を並べ、且つそれらを凌ぐものであることが明らかである。
1984年、37歳の西川徹郎は自らの表現の砦として、又、広く全国の有為の書き手に向けた文学としての俳句の追究の場として個人編集誌「銀河系つうしん」(第19号より「銀河系通信」に改題)を創刊した。創刊第1号の表紙には「友よ、批評の鍬を!」の言葉を掲げ、同題名の評論を執筆している。巻頭に置かれた「創刊の言葉」の全文を挙げてみる。
「今日、俳句表現の地平は、余りにも暗く、非文学的な風食に晒されてしまっている。/小誌は、わたしの個人誌ではあるが、 俳句表現の現在的問題を自己への問いとして苦悩し、言語表現の不可視の地平へ向って起ち上ろうと決意する人々に、望んで登場いただき、新鮮な批評と作品を発表していただくつもりである。/わたしは、個人誌というこの自在な〈場〉の獲得によって、 わたし自身の批評の眼を開き、苦悩をこそ表現の力として書き継いでゆきたい。俳句表現の新たな展開を模索するために、細やかながら小誌を非定期的に発行しつづけてゆくつもりである。」
「銀河系つうしん」の創刊は、『無灯艦隊』以後、第二句集『瞳孔祭』を経て、第三句集『家族の肖像』(1984年・沖積舎)の刊行を目前にしつつ、西川徹郎が、旧弊な俳句観と結社主義に囚われた人々からの激しいバッシングを受けながらも果敢に踏み出した、俳句革命の道程であった。西川徹郎個人への謂われ無き誹謗と中傷とが飛び交う中で、北海道詩人協会会長を務めた新妻博(1917~2010年)、越澤和子らは、西川徹郎支持の態度を明らかにし、俳人小南文子(1923~2010年)・加藤佳枝らは「銀河系通信」のスタッフを買って出て、西川徹郎の文学活動を支えた。1985年発行の第四号から、発行所を黎明舎と名付け、西川徹郎の文学活動の拠点とし、現在に至る。
新妻博は総合誌「北方文芸」(北方文芸刊行会)1986年7月号の俳句時評欄で「銀河系通信」の創刊はあくまで俳句革新を目指す西川徹郎の「ひとつの芸術上の正義」であり、積極的に支援したいと述べ、西川徹郎への支持を表明した。
俳人谷口愼也(1946~)は、〈世界文学としての俳句〉を提唱し「反季・反定型・反結社主義」を標榜して自らの文学を〈実存俳句〉と名付けた西川徹郎について、その著『虚構の現実―西川徹郎論』(1995年・書肆茜屋)中の「反定型」章に於いて次のように論じている。
「例えば松尾芭蕉の作業とは、体系化された中世美意識の相対化作業であった」「西川は定型ということを、結局は俳句という次元のみに限定せず、言葉や存在を束縛するものという、ある意味ではかなり拡大した形で捉えているのではなかろうか。もっと言えば、我々を致し方なく規定し束縛してくるこの日常的な現実の総体を定型とみなす彼の呪詛が働いているのではないだろうか。だとすれば、まさに定型とは、西川が生涯を賭けて闘わねばならぬモチーフであるわけだ」「『瞳孔祭』では、定型と戦う西川の姿が血と肉の匂いをさせながら展開されている(略)こちらが素直に西川の描く世界に入ってみれば、樹上に鬼がいるのも、隣家の馬が殴られるのも、あるいは父の陰茎を抜かんと喘いでいる光景も、妙なリアリティをもって、そこにそのまま在る(傍点著者)現実として、鑑賞することができるのだ。/今は亡き菅谷規矩雄が、『西川徹郎の世界』(筆者注、越澤和子編『秋桜 COSMOS別冊西川徹郎の世界』)の中で、実にいいことを言ってくれた。
「ことばが韻律に執する理由はただひとつ―リズムとは、詩の発生(傍点菅谷)の現前(プレザンス)にほかならない。この発生の、瞬間……というスリルをふくまなければ、俳句も、短歌も、むろん現代詩も、韻律として存在する理由はない。/西川徹郎があえてえらんだ悪戦の場が、なおまだ、遠くのわたしたちに、霊たちの泣き笑いするすがたを、その出現のスリルを、たんのうさせてくれることを期待して、この不格恰な走り書きを、ひとまずしめくくることにさせていただく。(菅谷規矩雄)」
「西川の俳句が、韻律の瀬戸際で書かれていることは確かであろう。散文と韻文のせめぎ合いの面白さ、そのスリリングさが読者に快感として伝わってくるのだ。〈父の陰茎を抜かんと喘ぐ真昼のくらがり〉にしても〈棺で帰ってきた児が屋根を這いあがる〉にしても、その散文化を食い止めているのが、まさに菅谷が言う詩の発生の現前(プレザンス)」なのだ。そして西川にとって詩とは「霊たちの泣き笑いするすがた」でもある」 (『虚構の現実』谷口愼也著、1995年・書肆茜屋)
又〈実存俳句〉に就いて西川徹郎は、講演録「口語で書く俳句―実存俳句の思想」で次のように述べている。前掲のこの講演は口語俳句協会が主催した2005年静岡県島田市での第五十回口語俳句全国大会記念講演。同大会幹事長田中陽と大会実行委員長加藤太郎の熱烈な要請によって行われたものであった。
「私の提唱する「実存俳句」の「実存」とは何か、と言うと、それは、「人間のありの儘の姿」を口語で書く俳句のことであります。
/「人間のありの儘の姿」こそ人間の真実の相であり、「実存」なのであります。「実存」たるその「人間のありの儘の姿」は、同時に「人間の在るべき姿」をも映し出しています。/では、「人間のありの儘の姿」とは何か。「人間の在るべき姿」とは何か。/私の第九句集に、書き下ろしで1145句を収録した『天女と修羅』(沖積舎)が1997年に刊行されています。この句集は、全て漢字とカタカナ表記の句集です。
秋ノクレタスケテクレト書イテアル 徹郎
端的に言えば、この句に表われた「タスケテクレ」の絶叫が、人間の〈実存)です。この「タスケテクレ」という声は、何処までも人間という存在の「内部の声」であり、「内奥の声」であります。あるいはそれを、人間の「末期の声」、「後の無い、最期の声」と言っても、「声にならない声無き声」と言ってもよいでしょう。私たちは皆、この「タスケテクレ」の、声にならぬ声無き声を内部に抱えながら、自らそれを発し、自らそれを聞きつつ日々の生活を為しているのであります。/実に、この「タスケテクレ」という内部の声こそが詩であり、生存の告発であり、詩表現といわれるものの原形態です。極論すれば、この内部の声の聞こえぬものなどは詩でも文学でもないのであります。この内部の声を書きとどめ得て初めて、詩を、文学を名乗ることが出来ると言って過言ではありません。」
(「俳句原点」117号、口語俳句協会刊、2006年/「銀河系通信」第19号・黎明舎)
Ⅳ 少年詩人の系譜─永遠の夭折者
戦後日本を代表する〈知〉の巨人、詩人・思想家吉本隆明(1924年~2012年)が執筆した詩人論は数多いが、絶賛の筆を走らせた日本文学史上の詩人は、源実朝・宮沢賢治・西川徹郎の三人である。すなわち『吉本隆明 初期ノート増補版』(川上春雄編、1970年・試行出版部)収載の「宮沢賢治論」(後に『宮沢賢治論』(1996年・ちくま文庫)、『源実朝』(1990年・ちくま文庫)、『西川徹郎全句集』(2000年・沖積舎)収載の「西川俳句について」の三編がそれである。
吉本隆明が「一冊の著作を、宮沢賢治について最初にもちたい」と願った『宮沢賢治』論の原稿は、『初期ノート』(1964年)刊行時には、「戦後の洪水で失われた」(吉本隆明、同書所収「過去についての自註」)とされていた。1947年9月、関東・東北地方を襲ったキャスリーン台風は、東京東部の低地帯を完全に浸水させたのだった。しかし三年後、吉本隆明研究の第一人者川上春雄(1923年~2001年)がノート9冊を発見し、『増補版』として収載、70年に刊行されたのである。
「西川俳句について」は、先に『秋桜COSMOS別冊西川徹郎の世界』(越澤和子編、1988年・秋桜発行所)に「西川徹郎さんの俳句」という評論を寄せていた吉本隆明が、編者に「いずれもう一度西川論を書きます」という私信を認めていたものが実現したものである。
宮沢賢治(現代詩)、源実朝(短歌)、西川徹郎(俳句)について成されたこの三編の「少年詩人」についての評論には、吉本隆明が明らかにした詩とは何か、詩人とは何か、という問いがある。例えば〈実朝的なもの〉について、吉本隆明は「第一級の詩心の持主」又、「暗殺によって夭折したもの」であることを挙げる。これは吉本隆明が実朝が「少年詩人」であるということを確認した言葉ではないか。実朝に、
大海の磯もとどろによする波われてくだけて裂けて散るかも 源実朝(『金槐和歌集』)
という高名な歌がある。死の前年(実朝27歳)に詠まれたもので、『金槐和歌集』貞享板本(1687年板行、716首)に収録された。まず海が大きく捉えられ、波が分割拡大され、スローモーション画像を見るように時間と空間がダイナミック且つ微細に描かれる。その波の穂先にやがて霧消する自らの行く末までも見据えている、夭折者たる宿命を生きる実朝の透徹したまなざしがある。
因みに実朝の『金槐和歌集』には二系統があり、貞享板本の他に、定家所伝本とも呼ばれる建暦三年本(1213年刊・666首)がある(実朝22歳)。鎌倉時代の史書『吾妻鏡』の詳細な記述に拠れば、実朝は14歳から和歌を詠み始めており、師として選んだ藤原定家(1162~1241年)に歌稿を預けていた。「鎌倉の大臣」を意味する「金槐」という歌集名は没後つけられたもので、この歌稿が『金槐和歌集』の大半を成す。その意味からも同集は、日本の詩歌史上の十代作品集の一つと数えられるだろう。
太宰治は小説「右大臣実朝」(1944年)の中で実朝に未だ12歳の公暁に対し、「學問ハオ好キデスカ/無理カモ知レマセヌガ/ソレダケガ生キル道デス」と言わせている。実朝こそ、常に極限状態であった生涯にもし七百余首の歌を詠まずにいたならば、生きることは不可能だっただろう。
西川徹郎は、1984年「銀河系通信」(当時「銀河系つうしん」)創刊号の「編集後記」を「宮沢賢治の『春と修羅』第一集は、次の言葉ではじまっている」と賢治の詩を引用することから書き出し、次のように結んでいる。
「私の家の裏山には、今日、桜の花が開き始めた。葉桜となる五月末の頃には、共著の評論集『俳句1984』(南方社刊)が刊行される。また、六月には、私の第三句集『家族の肖像』も、東京の沖積舎からいよいよ刊行されるであろう。ともに多くの志ある方々のご一読を願ってやまない。少なくとも、そこには、〈書く〉という行為に生活の全てを投げだしてきた私の必死の言葉が開花しているはずであるから」「近頃、ふしぎなくらいに、賢治の詩集を読んで胸を熱くした私の少年の日が想い出されてくる。私の母校の中学校の若葉や青草の匂いが甦ってくるのだ。そして、それとともに、その少年の日から今日までの間に、苦しみの〈生〉の現場からばたばたと姿を消していった多くの縁者たちの言葉が、私には、ふしぎに懐しく思われてくる。/父よ。あるいは、私は、書く行為の持続の中で、どこかで、すでに不在者でしかないあなたに、なされるはずのない再びの出会いを成し遂げようと必死になってきたのであったのかもしれない。もし、仮りにそうであったとすれば、小誌「銀河系つうしん」は、〈不在〉の読者へこそ向けて発信しつづけられてゆく霊性の便りなのだと言ってもよいはずである。そのとき、それは、たとえば、銀河系の彼方から不断に私たちの〈生〉に向けて送り届けられている宇宙の淡い光りにも似て、言語表現の〈現場〉を青白く照らしだすはずである。/このように考えるとき、〈わたくしという現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です〉という賢治のことばが、哀しい傷みをともなって、私の全身に染みわたってくるのがわかる。/何はともあれ、私は、この傷みと苦しみの中から、力あるかぎり、小誌「銀河系つうしん」を発信しつづけてゆこうと思う。」西川徹郎の作品は、現在も〈生〉を賭けて創造され、未知の、そして〈不在〉の読者へと向けて発信され続けている。
西川徹郎は詩や詩人について、常にこのように語っている。
「詩を書くということが無ければ一日たりとも生きることが出来ないという一点に於いて、彼らは詩人であり、それが詩というものが発生する根拠なのだ。人間が生きることの根拠と、詩を書くという行為が、詩人にとっては全く同一の問題の中に提示されていなければならない。」(「創作ノート」)と。又、西川徹郎が自らの彷徨の時代について書いた「睡蓮の夢―赤尾兜子」と題するエッセイが同人誌「豈」九号(1985年・豈の会)に発表されている。それは一九六六年赤尾兜子(1925~81年)に「初めて会った頃―、」と書き出されている。
「(略)昭和四一年の春、ぼくは、生きることの不安と焦燥に胸掻き毟るようにして京都の暗い下宿屋の二階に住んでいたのであった。
暑苦しく薄暗いその四畳の小部屋は、不眠に窶(やつれ果ててしまった僕の頭の中の重苦しさに似ていて、一日を通して日が入ることはなかった。ぼくはその日当たりの悪さに、ぼく自身が人生として背負い込んでしまった不幸を予感し、しかも、その予感が醸しだす不安と戦うように来る日も来る日も、ただ俳句を書き続けて暮していたのであった。おそらく、ぼくの青春の日の〈生〉は、俳句を書き続けることで辛うじて維持されていたのであった。」
西川徹郎は、
「少年詩人とは永遠の彷徨者・永遠の詩の探究者・永遠の夭折者のことである。」(「創作ノート」)
と語っている。「僕の青春の日の〈生〉は、俳句を書き続けることでかろうじて維持されていた」と述べる西川徹郎の文学は、彼が紛れもなく少年詩人であることを証している。少年詩人とは、単に年若くして詩を書く者のことではない。詩人とは詩とは何かと問い、詩を探究し、詩を達成せんと志す人のことであるから、少年詩人とは〈天才〉の異名であり、詩を以て己の生を夭折した人のことである。
この場合は肉体的な死には関わりがない。肉体的な生き死にを超えて、彼は永遠の夭折者としての生を生き続けるのである。西川徹郎が現在も多数の論者から幾度となく〈天才〉と呼ばれ続けているのは、西川徹郎が紛れもなく少年詩人であるからに他ならない。
吉本隆明は、『西川徹郎全句集』(2000年・沖積舎)所収の「西川俳句について」の中で、
「西川徹郎にとって青春期の表現はどこにどんな形式でありえたのだろうか。かれの俳句は読むたびにわたしにそんな設問を仕かけてくるようにおもわれる。そして答えが見つけ出されるよりも、その設問がかれの俳句だったので答えがかれの俳句だったのではないという思いが、しきりにやってくる。これはいつもかれの句作を苦しくしただろうが、かれはどうやらすべての設問こそがポエジィなのだという詩観に到達していったのではないか。問いこそが詩であり、答えることが詩ではない。この詩観を持ちこたえたまま、かれくらい遠くまで歩んでいる者をわたしは知らない。もしかするとこれがかれに諦念の安直な道を択ばせない根拠なのに違いない。」と述べる。ここに西川徹郎の詩に対する考えが明らかにされていると同時に、吉本隆明自身の詩観の方位も明確に述べられている。
又、吉本隆明は続けて、「西川徹郎は俳人としては宿命的な不幸を背負っているといえようが、詩人としては誰も真似できないような晴れ姿ですっくと佇っていて天晴れといいたいような気がしてくる」(傍点筆者)と述べている。
詩人・文芸評論家飯島耕一(1930~)は、評論集『俳句の国俳諧記』(1988年・書肆山田)に於いて、
「西川徹郎には呪われた異端の匂いがする。呪われたというのは、しかし詩人にとっては光栄を意味している。」(傍点筆者)と述べている。
「宿命的な不幸」も「呪われた異端」も、「詩人としては天晴れ」であり「詩人にとっては光栄」なのである。いずれも「少年詩人=永遠の夭折者」を示唆するものであろう。
少年詩人の系譜を辿れば、松尾芭蕉も又その系譜に連なる。「おくのほそ道」(芭蕉没後八年後、1702年刊)に現代の照明を当てようとする『芭蕉道(ばしようみち)への旅』(2010年・角川学芸出版)を監修した森村誠一(1933~)は、同書に於いて芭蕉の「おくのほそ道」の完全創作訳を成し遂げて、表現者として常に未知の遠方へと向かった芭蕉に敬意と共感とを表した。1689年3月から8月まで半年にも及ぶ「おくのほそ道」の道程を終えて間もなく、芭蕉は「またぞろ旅恋(たびこい)が頭をもたげてき」て、「旅の疲れはまだ癒えていないが、九月六日、伊勢神宮の参拝を口実にして、ふたたび腰を上げ、舟に乗った」(森村誠一訳)のである。「舟に乗った」というさりげない結びであるが、芭蕉の詩魂の熾烈さを思わせる。この「おくのほそ道」の最終章に森村誠一は「おもえば芭蕉は終着駅のない途上の旅人であった。むすびの地は新たな旅立ちの地であった」と註を付している。芭蕉の半年をかけた「おくのほそ道」の旅には、同行二人として五歳年下の河合曽良(1649~1710年)が随行した。曽良とは少年詩人としてのもう一人の芭蕉とでもいうべき象徴的な存在のように思われる。
蛤のふたみに別れ行く秋ぞ 芭蕉 (「おくのほそ道」)
行き行きて倒れ伏すとも萩の原 曽良 (〃)
北の地に在って独学の灯をともす真宗学者西川徹真を激励し続けてきた浄土真宗本願寺派の勧学稲城選恵和上(1917~2014年)は、常々講演で曽良の句の「萩の原」とは〈浄土〉を指すと論じている。旅とはそのまま人生であり、詩人とは永遠の旅人である。それは森村誠一が西川文学を「永遠の青春性」と論じた(『永遠の青春性―西川徹郎の世界』2010年・西川徹郎文學館新書2)ことと、全く同じ意味である。彼らは死と隣り合わせの旅を懼れない果敢な飽くなき詩の追究者に他ならない。
又、森村誠一は連載評論「おくのほそ道新紀行」(「毎日が発見」2010年7月号・角川SSコミュニケーションズ)に於いて、
夏草や兵どもが夢の跡 芭蕉 (「おくのほそ道」)
無人の浜の捨人形のように独身 徹郎 (『無灯艦隊』)
を組み合わせ、
夏草や無人の浜の捨人形
とし、松尾芭蕉の〈蕉句〉と西川徹郎の〈凄句〉とに「運命的な相性が私には感じられる」と述べている。森村誠一が感じとった「運命的な相性」とは、松尾芭蕉と西川徹郎が共に永遠の詩の追究者であり、遙かに三百余年の時空を超えてこの両者のなかに永遠の夭折者・少年詩人を見た言葉なのである。
西川徹郎の文学は、もとより俳句形式が日本の伝統的な美意識や抒情性を断ち切ったところから直接「存在」を問う形式であるという理念と哲学に貫かれていた。青春の日に連日連夜明け方まで書き続け、さらに悪路を往く通学バスの窓際で、教室の片隅で、あるいは新城峠や夏休みに自転車を駆って訪れた隣市旭川市の神居古潭や常磐公園などの石狩川の河畔で書き継がれた青少年期の凡そ七万句の作品は、1974年西川徹郎26歳の年に第一句集『無灯艦隊』(粒発行所)として220句が精選され刊行された。この折りの出版費用は両親によって用意されたが、それは、正信寺二世住職で、病床にあった父西川證教(1914~1975年)の徹郎への最期の激励だった。證教は刊行の翌年の春三月に六十二歳で病没したのである。
『無灯艦隊』刊行と同時に、新しい俳句の詩人の登場に対して、全国から驚きと賞賛の反響が新城峠の麓の少年詩人のもとへ寄せられた。三橋敏雄・佐藤鬼房・鈴木六林男・前田鬼子・三谷昭・土岐錬太郎・近藤潤一ら新興俳句に連なる俳人たちや赤尾兜子・島津亮・林田紀音夫・阿部完市・仲上隆夫・堀葦男ら前衛俳句の陣営の俳人たちが絶賛。三橋敏雄(1920~2001年)は後に、「『無灯艦隊』自選百句」(アンソロジー『最初の出発』、1993年・東京四季出版)に就いて解説「出藍の句集」を執筆し、『無灯艦隊』は細谷源二を「発展的に継承」した「出藍の誉れの第一歩を示した句集」と呼んだ。又、2005年に刊行された『西川徹郎全句集』刊行記念論叢『星月の惨劇─西川徹郎の世界』(茜屋書店)に於いて俳人・評論家宗田安正(1930~)は「西川徹郎の俳句」と題し、赤尾兜子の「〈第三イメージ論〉のような前衛俳句の方法も押し流してしまう」と述べ、和田悟朗(1923~)は「生と死と性の集約」と題した論で、西川徹郎の『無灯艦隊』が「完全に兜子の峠を越えきっている」と述べた。すでに詩人鶴岡善久(1936~)は、西川徹郎第三句集『家族の肖像』(沖積舎、1984年)の栞文に於いて、集中の
祭あと毛がわあわあと山に 徹郎
を引き、「従来の新興俳句、前衛俳句がついに到達しえなかった一極地をこの句は占めている」と述べているが、『星月の惨劇』で俳人・編集者大井恒行(一九四八~)はそれを「超出への志」と呼んだ。大井は、西川徹郎が赤尾兜子の「渦」に関わった時代の貴重な目撃者であり、「超出への志」とは西川徹郎の俳句が、新興俳句と前衛俳句との双方を超えゆくもの、つまりは子規以来の俳句史の全てを超えることを意味しているのである。又、藤原月彦(1948~ 現、龍一郎)も西川徹郎と同時代に「渦」に関わった俳人であり、『無灯艦隊』の最初の購読者であるが、『星月の惨劇─西川徹郎の世界』に収録された「夜叉見る阿修羅」に於いて「何より西川徹郎の俳句を読んでいて実感するのは、この特異な世界には、まったく、追随者が存在しない。出現しえないということだ。『無灯艦隊』の上梓から、すでに四半世紀の歳月が流れているが、ついに西川徹郎俳句のエピゴーネンは出て来なかったではないか。真似ができないことが、まさに実存俳句の根拠ではないのか、と思う」と述べている。宗田安正は前掲の言葉に続いて、「その修羅の道を誰よりも遠くまで歩き続け、俳句史のなかで類のない新しい表現世界を樹立したのが西川俳句だった」と述べている。
当時北海道大学教授であった近藤潤一(1931~94年)は巻紙に墨書した長文の私信の中で、「(略)伝統否定の場から出された、これはもっとも良質な、魅力ある句集のひとつであることを私はすくなからぬ感動をこめて申すことが出来ます」(「粒」第三十号所収、1974年)と述べた。新興俳句の日野草城の門弟で文化人としても広く知られていた土岐錬太郎は1974年12月「北海道新聞」「俳壇回顧」で「新たな前衛の誕生を祝す」と俳句形式が生んだ天才の前途を期待し、最大級の祝意を述べた。短歌評論家菱川善夫(1929~2007年)も〈俳句革命〉を叫んで忽然と俳句界に現れた前衛の作家を寺山修司の再来の如く言祝いだ。寺山修司については西川徹郎は「銀河系通信」第19号(2006年8月)で特集を組み、寺山修司についての「寺山修司とは誰か」(2002年5月4日、北海道立文学館の特別展「寺山修司~きらめく闇の宇宙~」での講演録)及び評論「〈革命前夜〉の寺山修司」等五編を収載している。近藤潤一・菱川善夫の同僚であった国際的文学者、中国・北京社会科学院名誉教授千葉宣一が2010年8月1日付で、西川徹郎文學館の名誉館長に就任した。千葉宣一は1930年旭川市に生まれ、北海道大学大学院修了。元北海学園大学人文学部大学院教授。千葉宣一は『無灯艦隊』刊行時より、西川徹郎を日本モダニズムの代表的詩人と評価し、「松尾芭蕉は世界の詩の革命者、西川徹郎は世界文学の先端に立つ詩人」と称んで孤高の道を行く西川徹郎を激励し続けてきた。
ともあれ『無灯艦隊』という一振りの鋭利な剣は日本文学史に大きな亀裂を生ぜしめた。僅か十七音の俳句が、銀河系をも超える広大な未知の詩的宇宙を表現し得る世界で最もすぐれた詩形式であることが、文学史上に刻印されたのだ。西川徹郎の俳句革命の第一歩が踏み出され、以後今日までの五十年間、西川徹郎は〈世界文学としての俳句〉を提唱し、〈反季・反定型・反結社主義〉の俳句思想に基づく実存俳句を書き続けてきた。即ち季語季題に奪われてきた俳句文学のテーマを奪い返し、人生の総体を俳句の主題として、俳句表現の根本の理由を人間が生きる意味を問うことに置いたのだ。詩人の自由を奪い、国家の意志に跪(ひざまづ)かせようとする定型の作用に定型を以て抵抗する姿勢を貫いて、西川徹郎の全ての文学活動は営まれてきた。
後に芥川賞作家となる藤沢周(1959~)は「図書新聞」1988年11月19日号に於いて西川徹郎の最初の読本である『西川徹郎の世界』(「秋櫻COSMOS別冊」秋櫻発行所)を紹介し、「朦朧と形容したい彼岸と此岸の境界を、より鮮明に見てしまう十七音の末期の眼に、句作という自らの存在証明で抗っているのかも知れない。そんな一天才詩人の現場を目撃する一冊となっている」と書いた。藤沢周はその後「銀河系つうしん」第11号から13号まで「『町は白緑』―西川徹郎論」を連載、その一回目の論が『現代俳句文庫5西川徹郎句集』(1991年・ふらんす堂)に解説として収録されている。
2000年迄の集大成『西川徹郎全句集』(2000年・沖積舎)に、西川徹郎が少年の日より憧憬し続けてきた詩人・思想家吉本隆明は、前記の論文「西川俳句について」を執筆して絶賛、西川徹郎を「俳句の詩人」と称んで最長不倒の業績を讃えた。
詩人・評論家櫻井琢巳(1926~2003年)は『世界詩としての俳句―西川徹郎論』(2003年・沖積舎)に於いてランボーやボードレール、アポリネール等の詩作品と西川俳句との精密な比較検証を行い、彼等世界の詩人たちと西川文学が比肩することを実証した。又、同書で櫻井は、西川徹郎の、
イッポンノ箒ガ空ヲナガレテイル (第九句集『天女と修羅』1997年、沖積舎)
を掲げて、日本の一千年の詩歌史に対しても「西川俳句は、これ一本で『古今集』の美意識に対向できる、まれにみる力づよい文学性を持つ。(略)西川俳句はいま、『古今集』的な美意識をつきぬけてそびえる一連の高峰としてわれわれの前に立つ」と述べた。
法政大学教授で文芸評論家小笠原賢二(1946年~2004年)は『極北の詩精神―西川徹郎論』(2004年・茜屋書店)の中で、「西川ワールド」について、
日本海ヲ行ッタリ来タリ風ノ夜叉 (第九句集『天女と修羅』)
の一句を挙げ、その想像力と詩人吉田一穂(1898~1973年)の「形而上的思念は共振している」とし、
「遠く北方の嵐を聴きつつ……/弧状光を描く夢魔の美しきかな。/現身(うつそみ)を破つて、鷲は内より放たれたり。/自らを啄み啖ふ、刹那の血の充実感(みちたらひ)。/無風帯に闘争を超えて高く、いや高く飛翔し、/時空一如の階調に昏々と眠りいる黄金の死点。」(吉田一穂「鷲」)を挙げて「西川の幻想領域を彷彿とさせる」とし、「現身を破つて、鷲は内より放たれたり」について、「「現身」
を西川流に言い変えれば「実存」である。現実存在、事実存在の短縮形である実存とは、有限な人間の主体的存在形態を意味する。詩や文学とはつまり、この有限の「実存」から一羽の想像力の「鷲」を放つことである」と述べている。
川端康成賞や芸術選奨受章作家である稲葉真弓(1950~2014年)は、「読売新聞」2005年10月の連載コラム「言葉を生きる」で寺山修司に続き西川徹郎を取り上げ、同29日付で「喚起されるイメージに導れて句を読んでいると、私の中にも無明の「思念原野」がぼうぼうと広がる。(略)現実と非現実を自在に行き交う十七文字に、「言葉」の持つ無限の力を思い知らされもする」と述べている。
西川徹郎作家生活五十年の成果に就いて、日本大学名誉教授で「泉鏡花論」等の著者として高名な文芸評論家笠原伸夫(1932~2017年)は『銀河と地獄─西川徹郎論』(西川徹郎文學館新書1、2009年刊)に於いて「西川徹郎の方法はつねに尖鋭であり、原則十七音の俳句形式への断絶と連続という背理的な形での自負につらぬかれている。(中略)一言でいえば反俳句の俳句―反伝統の伝統である」「西川徹郎、異形の天才というほかはない」等と述べる。
2009年5月西川徹郎文學館で行われた来館記念講演で西川徹郎の実存俳句を「西川凄句(せいく)」と命名した作家森村誠一は、『永遠の青春性―西川徹郎の世界』(2010年・西川徹郎文學館新書2)の後記に「西川凄句は日本の文学遺産」「生死の境界を超えた永遠の絶唱である」と銘記した。
又、西川徹郎の十代作品を「世界文学」と呼ぶ「神奈川大学評論」の創刊号からの編集専門委員を務める文芸評論家小林孝吉(1950~)は、『銀河の光 修羅の闇―西川徹郎の俳句宇宙』(西川徹郎作家生活五十年記念出版、西川徹郎文學館新書3)に於いて「西川徹郎は、ついにダンテやドストエフスキー、日本では宮沢賢治や埴谷雄高などごく少数のものしか到りえない、生の惨劇の究極の地点=魂の高い峠に立ったのだ。そこには〈絶対の救済〉=〈銀河の光〉が満ち溢れている……。」と述べた。
『北一輝論』(講談社学術文庫)等の著者で革命評論家として名高い松本健一(1946~2014年)は、西川徹郎へ宛てた書簡(2010年6月1日付)で「西川実存俳句が〈世界文学〉への歩みを続けていることは間違いない」等と述べている。
『物語の哲学』『科学の解釈学』等の著者で東北大学総長特命教授で日本哲学会会長を務める言語哲学者・科学哲学者野家啓一(1949~)は、「読売新聞」(2010年6月18日付)書評欄で『永遠の青春性─西川徹郎の世界』を紹介し、「「わが黄金伝説」と題する西川の自選三百句が収録されており、そこに展開される血族の修羅と死の予兆に彩られた風景は、寺山修司の歌集『田園に死す』を想起させる」と述べた。
『無灯艦隊』の刊行以後、今日までに、西川文学の総体としての〈無灯艦隊〉は、日本文学史に高遠な航跡を拓き続けているのである。
因みに、十代に短歌によってその文学活動を始めた作家の一人として、宮沢賢治が挙げられる。賢治は十四歳の年即ち1911年1月、盛岡中学二年の三学期から短歌を作り始めるのであるが、一ヶ月前に盛岡中学の十年先輩の石川啄木の『一握の砂』が刊行されており、この年から盛岡中学校では、啄木張りの短歌が流行したとのことである(「作品解説」原子朗『群像日本の作家12 宮澤賢治』1990年)。賢治は約11年間短歌を創作したが、「異稿をふくめて千余首の歌を残していながら、短歌だけで見るとすれば、ユニークな連作歌群などありはするものの、ついに独自の歌風といえる賢治短歌の自立の様式を私たちはそこに見いだすことができない」と、詩人・文芸評論家原子朗(1924~2017)は述べている。宮沢賢治の1919年(19歳)作の「夜をこめて行くの歌」と題された連作から二首見てみよう。
みかづきは幻師のごとくよそほひて
きらびやかなる虚空をわたる
みがかれし
空はわびしく濁るかな
三日月幻師
あけがたとなり (「宮澤賢治短歌考」岡井隆『群像日本の作家12宮澤賢治』より引用)
二行、又は四行等に分かち書きするところに、啄木の三行書きの短歌の影響が見られるが、啄木短歌の形を借りて童話の一節を、絵画的イメージで描き出したスケッチの感があり、短歌という定型詩に対する意識はむしろ希薄といえる。
宮沢賢治の死の前日(1933年)に書かれたという「絶筆」も短歌であった(「生命と精神―賢治におけるリズムの問題」原子朗『群像日本の作家12宮澤賢治』)。
方十里稗貫のみかも稲熟れてみ祭三日そらはれわたる
病(いたつき)のゆゑにもくちんいのちなりみのりに棄てばうれしからまし
(「生命と精神―賢治におけるリズムの問題」原子朗『群像日本の作家12宮澤賢治』より引用)
宮沢賢治の没年となった年は豊作で、賢治はその安堵感の中で死を迎えたことが辞世の二首に表れている。全短歌作品を検討出来なかったが、短歌は賢治にとって親しいものではあったものの、〈生〉の根拠としての詩の形式とはなり得なかったと思われる。
他に十代の詩歌作品集としては、石川啄木が二十歳で出版した詩集『あこがれ』(1905年)や、十代に書かれた俳句九百句を収める寺山修司(1930~83年)の『寺山修司俳句全集』(宗田安正解説、新書館、1986年)等がある。
西川徹郎には、先に『決定版 無灯艦隊―十代作品集』(2007年・沖積舎)があり、この度本書『西川徹郎青春歌集―十代作品集』を刊行する。俳句と短歌という二ジャンルに亘り、十代作品集を著書として持つ詩人は日本文学史上に恐らく例が無い。
Ⅴ 少女ポラリス
しらしらと朝降る雪を映すかに白かりしかの君が頬かな (淡雪)
歯磨き粉の匂ひして雪降ってゐる学校帰りの君の幻 (歯磨き粉の匂ひ)
初恋の君と別れて来し日より歯磨き粉の匂ひして雪降ってゐる (〃)
西川徹郎少年が初恋の少女と出会ったのは中学時代のことであった。少年時代の自分自身について、後年西川徹郎は「秋風、鶏足に」(『秋桜COSMOS別冊西川徹郎の世界』)という文章の中で次のように語っている。
「昔、貧しかったぼくの家では、庭先の日当たりの悪い空地に、鶏を数羽飼っていた。/孤独で自閉症ぎみの少年であったその頃のぼくは、暇さえあれば、庭中に彼女らを追い回したり、時には窓から侵入してくる彼女らを物陰に隠れていて、大声を挙げて驚かしたりして遊んだ。彼女らは、当時のぼくの唯一の友達だったのである。」
家畜として飼っていた鶏や山羊、寺に迷い込んで来た犬や鳩や門前に捨てられていた猫、寺の飼猫の母猫ミーコとその子猫たちが少年の友達だった。動物たちは不思議なくらいよく少年に懐いて、少年が学校から帰るのを待ちかねたように現れては少年の後を付いて回った。迷い鳩は、学校から帰った徹郎少年が玄関先で「ポー、ポー」と呼ぶとさあっと裏山から飛んできて、少年の肩に止まるほどであった。孤独な少年の友達はこれらの小動物、そして自在に少年の心と体を何処までも運ぶ口笛と自転車であった。
まっ青な夜空があれば口笛を北上夜曲吹き鳴らすかな (口笛)
本書の作品を整理していたこの春(2010年)、西川徹郎は思い出せなくなっていた「北上夜曲」のメロディーを試みに口笛で吹いてみたという。頭ではすっかり忘れ去っていたメロディーを唇が覚えていて口笛は朗々と鳴り響き、驚いたとのことである。自転車については、西川徹郎のエッセイ集『無灯艦隊ノート』(1998年・蝸牛社)の「峠の狂人」の章や第九句集『天女と修羅』(1997年・沖積舎)後書等に、無心に自転車を漕いで新城峠に登るのが常だった少年期の美しい記述がある。
「少年の頃、私は幾度も自転車を駆って独りで峠へ上ぼった」「満月の夜などは殊更に幻想的な思いを掻き立てさせてくれる。月の光を浴びて蘇生したかのように飛び回る秋津たちの美しさは、私にはこの世のものとはどうしても思うことが出来ない。(略)両耳をそば立て聴き澄ますならば、忽ち月の光を浴びて羽ばたく村じゅうの無数の秋津たちの羽擦れの音が余りに鮮明に聞こえて来てわが耳を疑うのである。/仲秋の満月ともなれば、少年の頃の私は決まって深夜の寝床を抜け出し、その余りにも澄み切った美しい轟きを聴きに自転車を駆ったのである。」 (句集『天女と修羅』後書)
因みに、最初の結婚の日々の眩しいばかりに溌剌とした妻を描いた
妻よはつなつ輪切りレモンのように自転車 (『瞳孔祭』)
以来、〈自転車〉は今日まで書かれ続けており、西川文学の数多いキーワードの中の一つである。
剛毛生えた自転車突如走りだす (『家族の肖像』)
妻のゆうれいビルにぶつかる自転車は (『死亡の塔』)
月夜茸むしんに走る自転車は (『町は白緑』)
自転車は屋根駈け巡る銀の花 (『桔梗祭』)
自転車に乗るため舌は裂けている (『月光學校』)
白い切れで自転車をぐるぐる巻きに (『月山山系』)
繃帯の自転車を父と思い込む (〃)
蒼蒼と自転車漕いで戻る抽斗 (〃)
青蓮ハ自転車漕ギツツ村越エル (『天女と修羅』)
杉ノ木ノテッペン銀ノ自転車懸カル (〃)
くちなわで括られ死後の自転車は (『わが植物領』)
自転車という渦巻銀河弟よ (『銀河小學校』)
動物たちと遊び、自転車を駆る孤独な西川少年の中学時代に訪れた文学世界への憧憬と詩歌への傾倒は、都会からやって来た少女に対する初恋と重なり合う。幼少期に親しんできた既視の世界から徹郎少年を未知の世界へと誘い行くものが、文学であり初恋の少女であった。
俳句革命に人生を賭けた詩人西川徹郎にとって、殊更に短歌を以て謳い上げた初恋の少女とは誰だったのか。その少女とは西川徹郎が一途に求め続ける詩的真実の異名、ポラリスとでも名付け得るべきものではなかったか。
君と来て東寺の塔の尖端のひときは暗き星を見てゐる (秋の風)
京都での在学生活を題材にした短歌作品には、初恋の少女とオーバーラップして、歌い舞いギターを弾く伎芸天のような、或いは歌いつつ人を水底に誘うセイレーンの如き愁いを帯びた少女が現れる。
水際に棲みて水より透きとおるかげろふのごときひとを祈れり (蜉蝣)
涙(さし)ぐみし瞳に浮ぶ賀茂川の水の色など美しかりき (賀茂川)
君がため涙流るる賀茂川の岸の菫は星屑なりき (〃)
泣くほどに賀茂川恋し夕空を命の如く雁飛びゆけり (秋の風)
賀茂川の水より暗き水滴がわが掌に落ちぬ君が目(まみ)より (〃)
君が胸に小雨降るなりわが胸に雪の降るなり祇園よさらば (祇園よさらば)
彼女等こそ、西川少年が心を奪われ追い求めた、芸術を司る美の女神たちだ。追っても追っても幻のように現れては消え、消えては現れる。「黄漠奇聞」(稲垣足穂、新潮文庫『一千一秒物語』所収)の月影を追う王のように、またついに海に浮かぶことがないまま渡宋の夢と共に砂浜で朽ち果てた唐船を建造した源実朝のように、見果てぬ世界への憧れは詩人の身を焼く。
血の駱駝忽ち沙上の華となる (第十三句集『銀河小學校』二〇〇三年)
船大工螢に船を焼かれたり (第六句集『桔梗祭』一九八八年)
西川徹郎にとって初恋の少女とは、永遠に求め続けるべき青白く輝く極北の星であった。
「極北」について、真宗学者西川徹真が2000年7月に創刊した『教行信証研究』の第三号(2009年、黎明學舎/茜屋書店)に掲載された西川徹真の論文「「正信念佛偈」造偈の由序」の註に「北極」についての記述がある。「北極」とは「真理のありか」を指し示す言葉で、「浄土三部経や真宗の七祖聖教にはないが、空海の『三教指帰』に出(い)で来る」と述べている。但し西川徹真の同論文は、空海の解釈とは異なり、「北極」という言辞を以て釈迦一代の説法の帰結が阿弥陀佛の本願であることを示し、『大無量寿経』に釈迦が説く阿弥陀佛の本願が人類の究極の帰依処であることを論じているのである。
文学に於いても同様に、真実の文学は人間を死へ向かわしめるのではなく、必ず人間を生かすためにはたらく。ダンテやドストエフスキー等の文学が成し遂げているように人生の苦悩の北壁を超えてゆく人間の姿を描き出すのが世界文学なのだと西川徹郎は常に語っている。
石川啄木は『一握の砂』『悲しき玩具』を以て人生の苦悩の相をありのままに詠った。西川徹郎の実存俳句に準えれば石川啄木の歌は実存短歌と呼んでいい。歌人・文芸評論家高橋愁(1942~)は、西川徹郎と石川啄木との共通点を見出し、啄木を現代に甦らせて西川徹郎と遭遇させ、啄木が西川徹郎の実存俳句を論ずるという奇想天外な評論小説『わが心の石川啄木』(1998年、書肆茜屋)を書いた。青春といえる年代に人生のぬかるみ道を何処までも喘ぎつつ歩む啄木の文学は共感を呼び、今も読み継がれている。しかし人間の実存を描きつつ実存を超える道を照らし出す、〈光を書く文学〉が世界文学としての西川俳句なのである。青春の日に愛唱した啄木を超え、西川徹郎の文学は、今、〈世界文学〉としての光輝を放つ。
大学を中退し、初恋の少女とも別れた二十歳の西川徹郎は、絶望の中に果てしなき彷徨を続けていたが、ある夏の日、札幌大通公園の青草の上で、書店で見つけたばかりの吉本隆明の『初期ノート』(発行人・川上春雄、試行出版部)を開く。吉本隆明が自分と同じ年代に書いた強靱で透徹した詩と宮沢賢治論などの精緻な思索とを目の当たりにした西川徹郎は、作家としてこうしてはいられないと身震いする。この傑出した詩人・思想家吉本隆明に対峙すべき文学作品を書き上げなければならない。それは西川徹郎が〈俳句の詩人〉として生きる決意を固めた瞬間だった。
ところで、宮沢賢治は十四歳であった1911年、盛岡中学在学中に石川啄木の『一握の砂』に喚起されて短歌を書き始め、それが彼の文学活動の端緒になった。吉本隆明は1943年、19歳の年、その「宮沢賢治論」の中で「賢治さんを見ならうても賢治さん以上の人になってみせる」と述べた。少年の日の吉本隆明も又、宮沢賢治を凌ぐ詩人にならんと決意したのである。そして西川徹郎は、1967年20歳の年に吉本隆明と文学を以て対峙しようとする詩志を燃やした。ここに石川啄木─宮沢賢治─吉本隆明─西川徹郎と続く日本文学史の一筋の道を見渡すことが出来る。
少女ポラリスの役目はしかし、終わったわけではない。西川徹郎の文学世界を私たちは、第一句集の題名の如く、闇夜に出立し、降り注ぐ銀河の光を浴びて未知の世界文学の航路を開く〈無灯艦隊〉と名付けることが出来るだろう。「無灯艦隊」という言葉はタイトルとなっていながら実は、初版本の『無灯艦隊』の作品中には登場しない。十二年後に初めて、同世代の俳句作家で、西川徹郎と共に同人誌「豈」を創刊した攝津幸彦(一九四七~九六年)や「季刊俳句」(冬青社)の創刊と刊行によって西川文学を推進し、自らも西川徹郎第七句集『桔梗祭』(一九八八年、冬青社)伴載の西川徹郎初の本格的な作家論「蓮華逍遥―西川徹郎の世界」100枚を執筆した宮入聖(1947~)らが現代俳句の牽引力とすべく定本として刊行した『定本 無灯艦隊』(1986年、冬青社)に「無灯艦隊」という言葉を含む作品、
海女が沖より引きずり上げる無灯艦隊
が収載されたのである。この「海女」こそが、少女ポラリスではないか。筆者はかつて「「秋ノクレ」論―西川文学の拓く世界」(『星月の惨劇─西川徹郎の世界』所収、2002年・茜屋書店)に於いてこの作品を、沖の海底に在る〈無灯艦隊〉が「海女」によって海上に引きずり上げられ、西川徹郎の文学世界が姿を現した、と読み、西川文学世界の登場とした。だが今、少女ポラリスとは、波間の〈無灯艦隊〉を銀河輝く天空へと引き上げ、西川徹郎を永遠の真実・極北の真理へと差し招く詩神であると思わずにいられない。恰も『ファウスト』に於いてゲーテが、
永遠の女性が
われらを引きあげて行く (『ファウスト』「世界文学全集」高橋健二訳)
と嘆じたように――。
『西川徹郎青春歌集―十代作品集』は真摯に詩的真実を求め続けた少年期の詩人の魂の軌跡が一少女への憧憬の足跡と重なる希有の歌集であり、同時に一人の天才詩人の、日本の詩歌史に遺すべき永遠の絶唱である。ここに西川徹郎作家生活五十年を期して西川徹郎文學館叢書の第一巻として本書を刊行するものである。 (畢)
付記
本解説には実在する方の御名前が登場します。芦別市立新城中学校・北海道立芦別高等学校在学中に西川徹郎の同級生であった桑野郁子様には今回残念ながら連絡が取れませんでしたが、本書が学術的意味を持つ刊行物であることから敢えて当時の御名前を出させて頂きました。桑野郁子様をはじめ関係者各位には御了承をお願いすると共に深く感謝を申し上げます。
執筆中、偶々芦別市新城、銀河系通信発行所/黎明舎の書庫を整理したところ、保管されていた一束の書簡があり、奇しくもその中に昭和44(1969)年1月5日消印の桑野郁子様から西川徹郎へ宛てた年賀状が発見されました。桑野郁子様よりの書簡はこの一通のみで、西川徹郎よりの賀状に対する返信と思われます。徹郎の健康状態が良さそうであることに安心し、今後の各方面での活躍を期待する旨が端正なペン字で認めてあったことでありました。
◆本論の初出は2010年10月30日茜屋書店『西川徹郎青春歌集―十代作品集』解説/2015年刊行『修羅と永遠─西川徹郎論集成』に新城峠─詩聖西川徹郎伝③として改訂収録。『西川徹郎研究』第一集への再収録に際し、更に増補改訂を行った。
■斎藤冬海 さいとう・ふゆみ=作家・文藝評論家。真宗学者。日本女子大学文学部国文学科卒。北海道教育大学旭川校で學藝員科目履修。福島県文学賞(福島県・福島民報社共催)小説・評論部門元審査委員。短歌研究社編集部・角川書店「野性時代」編集部元勤務。現在、西川徹郎記念文學館館長・學藝員。学術誌『西川徹郎研究』及び「西川徹郎研究叢書」編集人。西川徹郎記念文學館賞選考委員。本願寺派輔教・布教使。龍谷教学会議会員。黎明學舎「教行信証研究会」世話人。著書に『斎藤冬海短編集』『月の出予報』。共著に『実演 真宗法話大辞典』(教育新潮社)『金子みすゞ 愛と願い』『わが心の妙好人』(共に勉誠出版)『新現代俳句最前線』(北溟社)。論文に「総論 アイヌの文学と作家」(勉誠出版『北海道文学事典』所収)、「新城峠─詩聖西川徹郎伝」(茜屋書店『修羅と永遠─西川徹郎論集成』所収)、真宗学論文に「真宗法蔵菩薩論」「獲得名号自然法爾ついて」等。芦別市在住。

第1句集『無灯艦隊』(1974年)
不眠症に落葉が魚になっている
夜明け沖よりボクサーの鼓動村を走る
海峡がてのひらに充ち髪梳く青年
流氷の夜鐘ほど父を突きにけり
京都の橋は肋骨よりも反り返る
晩鐘はわが慟哭に消されけり
首の無い暮景を咀嚼している少年
蝙蝠傘がふる妙に明るい村の尖塔
月夜轢死者ひたひた蝶が降っている
剃った頭に遙かな塔が映っている
癌の隣家の猫美しい秋である
秋は白い館を蝶が食べはじめ
無人の浜の捨人形のように 独身
男根担ぎ佛壇峠越えにけり
黒い峠ありわが花嫁は剃刀咥え
骨透くほどの馬に跨り 青い旅
暗い地方の立ち寝の馬は脚から氷る
馬の瞳の中の遠火事を消しに行く
『定本 無灯艦隊』(1986年・冬青社)
海女が沖より引きずり上げる無灯艦隊
無数の蝶に食べられている渚町
『決定版 無灯艦隊─十代作品集』(2007年・沖積舎)
こんなきれいな傘をはじめてみた祇園
群れを離れた鶴の泪が雪となる
屠鶏の流す泪は一番星である
剃刀が木星を忘れられずにいる
屠馬の視線と出会う氷の街外れ
屠馬は七夜一睡もせず星数え
第2句集『瞳孔祭』(1980年・南方社)
樹上に鬼 歯が泣き濡れる小学校
ねむれぬから隣家の馬をなぐりに行く
父の陰茎の霊柩車に泣きながら乗る
父はなみだのらんぷの船でながれている
瞳孔という駅揺れる葉あれは
妻よはつなつ輪切りレモンのように自転車
蝶降りしきるステンドグラスの隣家恐し
遠野市というひとすじの静脈を過ぎる
楢の葉雪のように積もる日出てゆく妻
第3句集『家族の肖像』(1984年・沖積舎)
食器持って集まれ脳髄の白い木
葉にまみれ葉がまみれいもうとはだか
浴室にまで付きまとう五月の葬儀人
鳥に食いちぎられる喉青葉の詩人
祭あと毛がわあわあと山に
家族晩秋毛の生えたマネキンも混じり
家中月の足あと桔梗さらわれて
四、五日で家食い荒らす蓮の花
まひるの浜の浜ひるがおの溺死体
自転車に絡まる海藻暗い生誕
倉庫の死体ときどき眼開く晩秋は
揺れる芒はおびただしい死馬か山上
畳めくれば氷河うねっているよ父さん
鳥がばたばたと飛ぶ棺のなか町のよう
猛犬である下駄箱は町を映し
第4句集『死亡の塔』(1986年・海風社)
雪降る庭に昨夜の父が立っている
少しずつピアノが腐爛春の家
校葬のおとうと銀河が床下に
おとうとを探して野原兄はかみそり
おとうとを野原の郵便局へ届ける
おとうとを巻きとる蓮の葉は月夜
かげろうが背を刺し抜いて行った寺町
股開き乗る自転車みんな墓地に居て
父と蓮との夜の手足を折り畳む
母も蓮華も少し出血して空に
空の裂け目に母棲む赤い着物着て
顔裂けて浜昼顔となるよ姉さん
紺のすみれは死者の手姉さんだめよ
姉は浜なす海は戸口に立っている
尖塔のなかの死螢を掃いて下さい
戸に刺さった蝶は速達暗い朝
なみだながれてかげろうは月夜のゆうびん
第5句集『町は白緑』(1988年・沖積舎)
遠い駅から届いた死体町は白緑
ふらふらと草食べている父は山霧
二階まで迷路は続く春の家
球根も死児もさまよう春の家
みんみん蝉であった村びと水鏡
秋津が秋の日の野の人を鷲掴む
滝というあばれる白馬が山中に
棺より逃走して来た父を叱るなり
藻にまみれた校塔仰ぐ少し荒れる日
石に打たれて母さんねむれ夜の浜
竹原に父祖千人が戦ぎおり
抽斗へ銀河落ち込む音立てて
床屋で魔羅を見せられ浦という鏡
階段で四、五日迷う春の寺
庭先を五年走っているマネキン
萩の間へ続く萩野を背負われて行く
第6句集『桔梗祭』(1988年・冬青社)
首締めてと桔梗が手紙書いている
妹を捜しに狂院の夏祭
遥かな萩野萩が千本行き倒れ
第7句集『月光學校』(未刊、2000年『西川徹郎全句集』所収・沖積舎)
月夜の谷が谷間の寺のなかに在る
おだまきのように肢絡みあう月の学校
花吹雪観る土中の父も身を起こし
剃刀を振り振り青葉が小学校へ
佛壇のなかを通って月山へ
マネキンも姉も縊死して萩月夜
寺屋根に引っ掛かっている白いマネキン
暗く裂けた鏡隣家の蓮池は
嵐の旅立ちゆえ妻抱くおだまきのように
天に瀧があって轟く父亡き日
池に沈んだ汽車青蓮となりつつあり
第8句集『月山山系』(1992年・書肆茜屋)
抽斗の中の月山山系へ行きて帰らず
月夜ゆえ秋津轟き眠られず
白髪の姉を秋降る雪と思い込む
第9句集『天女と修羅』(1997年・沖積舎)
婆数人空ヲ飛ブナリ春ノ寺
雲雀ガ雲雀ヲ啄ム空ハ血ニマミレ
顔裂ケタ地蔵モロトモ山畑売ラレ
未ダ眼ガ見エテ月ノ麦刈リシテイタリ
日本海ヲ行ッタリ来タリ風ノ夜叉
秋ノクレタスケテクレト書イテアル
第10句集『わが植物領』(1999年・沖積舎)
夢竟る馬が義足を踏み鳴らし
紋白蝶ト夜叉ガユラユラト飛ンデイル
夜叉ノ口モ比叡ノ谿モ裂ケテイル
第11句集『月夜の遠足』(2000年・書肆茜屋)
玄関で倒れた兄は冬の峯
雪虫も螢も兄の死顔かな
兄さんに降り注ぐ螢も薄羽かげろうも
ふらふらと遠足に出て行く死後の兄
月夜の遠出未だ熱がある死者の足
第12句集『東雲抄』(未刊、2000年『西川徹郎全句集』所収・沖積舎)
立小便する父葬花を担いだ儘
月の破船時計がボーンと鳴っている
烏よりも大きな蝶が浜町に
たすけてくれぇたすけてくれぇと冬木たち
椿墜ち百千の馬車駆け出さん
「藝術とは死との関係である」天上裏
墓は永遠に裸である 氷雨
犬から解けた繃帯が街の外れまで
佛身は青野時々瞬くは
走らねば蜻蛉に食われてしまう弟よ
父さんと一緒に死んでゆくさなだむし
山寺で死なないためにたたかう空の鯉
第13句集『銀河小學校』(2003年・沖積舎)
小學校の階段銀河が瀧のよう
廊下に映る銀河夜まで立たされて
筆入にカミソリ銀河を隠し持つ
井戸に落ちた弟と仰ぐ天の川
銀河が喉に溢れる虫籠のキリギリス
北枕初夜を銀河が身を反らす
夢魔が来て夜な夜な掴む木の葉髪
洋服箪笥に銀河が懸かる兄の家
絶叫しつつ散る兄亡き家の山茶花
惨劇という名の月夜茸が生え
キリギリスの羽脈に透る銀河系
鉄窓より名月を観るキリギリス
死んで別れた妹雛の頬に月
寺の溷に銀河がだらりと垂れ下がる
北枕で見た夢をノートに書き切れず
第14句集『幻想詩篇 天使の悪夢九千句』(2013年・西川徹郎文學館/茜屋書店)
冬烏地獄の空を低く飛ぶ
抜かれるときぎゃあと声出す秋の稗
誰も知らない海が墓穴の中に在る
盲学校幻の橋に雪降らせ
ぎゃあと叫ぶ蝶が白馬を襲う時
祇園の雪のお鶴が少しずつ狂う
お鶴の翼鳥辺野に雪降るよう
井戸から揚がった花嫁を見に山だかり
花嫁は井戸から揚がる白馬かな
佛身という渚の道が奈良に在る
後架の窓の青竹林にぞっとする
半盲の母が羽化する夕まぐれ
秋に逢えば猛禽が棲む君の胸
永遠に悲鳴を上げる寺の樺
桜並木が義眼に映る月夜ゆえ
産道で出会った悪魔美しき
産道と死出の山路が続きおり
山の廃校柱時計が鳴っている
網目から鶏地獄を観ていたり
佛壇の中を三年放浪し
屋根裏遊び西日に焼かれ尽すまで
繃帯で白馬をぐるぐる巻きにする
首の長い姉妹が空飛ぶ夕かな
炎天の旅は犬よりも淋しけれ
いのち尽き果ててから読む『いのちの初夜』
父の背骨の谷川うねりつつ流れ
谷川をまっ青な河童が流されてゆく
ゆめさめるまで月の食事をして過ごす
桜の國の果てまで縄で連れられて
胸に刺さった遠い帆のよう兄の嫁
蜻蛉の青い川が流れてゆく頬を
死馬を孕んだ馬が嘶く山櫻
夕映えが湖畔の寺を血染めにし
冬浜に白い義足が落ちている
私の耳を啄み叫ぶ浜千鳥
野のバスを襲う紋白蝶の群れ
夕月は湖底で叫ぶ白い鶴
死へ急ぐ父白髪靡かせ馬のよう
友禅の姉はひとすじ身を流し
雪降る秋の寺を木乃伊と散策し
白粉の舞妓と木乃伊が入れ代わる
清水寺の舞台で木乃伊と雪の舞
夕茜あかあかと火矢が峠越え
小学校で鬼籍の人を数え切れない
隣人の眼を突く馬上で身を伸ばし
隣の馬の喉に食いつく青い馬
病院裏の川を流れてゆくマネキン
鷲ほどの揚羽飛ぶ町小焼けして
波の彼方の帚の国に父住むらし
たくさんの舌が馬食う村祭
村人の舌で刺された父はサルビア
井戸に落ちた夜の太陽を覗き込む
白樺は繃帯の父か裏山に
さまざまなはらわた流れる秋の川
五月の兄の瞳孔夜の青空は
自転車の妹映る月の湖
彗星を仰ぐ湖底の寺の屋根
玄関先で血涙が出て止まらない
荒れる日恐ろし隣家の空の鯉
佛壇から落ち易し苦悩する桃は
遠く哀しい旅を白髪の自転車で
庭に植えた人形に朝夕水を遣る
大きく育った悪魔連れ出し寺参り
二日ほど家に還る秋津となり兄は
箪笥の上の人形は五年慟哭し
死ねぬゆえ自転車跨ぐ白い秋
十七文字で遺書書くすぐに死ねぬゆえに
蜻蛉の羽根で詩を書く妹遠きゆえ
秋風に空飛ぶ案山子を見てしまう
遠雪崩白い別れでありしかな
寺の畑の案山子狼のように吼え
父さんもうだめだ背の穴に燕棲む
こんなに遠い帚地獄まで来てしまった
未だ生きている案山子を背負い枯野行く
叫ぶ蟋蟀床下の銀河系ならん
妹が跨がる白馬血にまみれ
ヒヤシンス三歩歩けば黄泉が見え
螢野の惨劇見える障子穴
ハンケチが遠くて瞼は月夜の津波
雪虫に混じって母飛ぶ夕かな
雪虫に攫われ空行く兄と姉
ゆうぐれの雪虫裾まで降り積もる
雪虫が積もって自転車走れない
妹の胎内雪虫地獄かな
死後三夜夢のように行く雪の楼閣
死後二日歌舞練場で舞うお鶴
夏草や無人の浜の捨人形
風の旅人よ集まれ新城峠大學
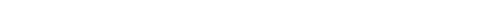

新城峠
私の生地芦別市新城は、北海道は上川郡と空知郡の境界に位置していて北の石狩川と南の空知川に挟まれた山峡の村である。私はこの北のはずれの寒村に淨土真宗の寺院の寺庭として生まれ育った。
村の最北端がなだらかな小さな峠となっていて、新城峠と呼ばれている。少年の頃、私は幾度も自転車を駆って独りで峠へ上った。峠に特別な何かが在るというのではないが、遙か南東のかなたには大雪山系の芦別岳や十勝岳等の峻峰がくきやかに白銀のうねりを露わに見せている。新緑や青葉の季節には一層に峰峰が強い意志を主張するかのように白銀を際立たせるのである。
秋は秋で言葉では遂に言い表わしようのない光景をこの峠は見せてくれる。山峡の村じゅうに棲む幾万匹、否、幾十万匹という無数の秋津たちが、透明なシルクの羽根をまるで旗のように打ち振るわせながら峠の頂をやすやすと往き交うのである。
満月の夜などは殊更に幻想的な思いを掻き立てさせてくれる。月の光を浴びて蘇生したかのように飛び回る秋津たちの美しさは、私にはこの世のものとはどうしても思うことが出来ない。はたして彼女らは燦燦と降り注ぐ月の光を真昼の日の光と過ちて飛び交うのであろうか。あるいは満月の余りに青々とした妖しい光に誘われて飛び交うのであろうか。峠の頂上に立つ時、私の身体にすれすれに往き交う彼女らの肢体が月の光に驚くほどにくきやかに見えて、その余りの美しさに言葉を失う。そればかりではない。両耳をそば立て聞き澄ますならば、忽ち月の光を浴びて羽ばたく村じゅうの無数の秋津たちの羽擦れの音が余りに鮮明に聞こえてきて我が耳を疑うのである。
中秋の満月ともなれば、少年の頃の私はきまって深夜の寝床を抜け出し、その余りにも澄み切った美しい轟きを聴きに自転車を駆ったのである。
(1997年『天女と修羅』後記抜粋、沖積舎)

風の日
初恋の君と別れて來し日より歯磨き粉の匂ひして雪降ってゐる
群れを離れた鶴の泪(なみだ)が雪となる
*
一九四七年九月、私は新城峠の麓の寺に生まれた。
少年の頃、ボードレールやランボーなど世界の詩人に憧れ、
学校から帰ると自転車を漕いで峠の頂に立つのが常だった。
春は遙か彼方に大雪山系の白銀の尾根が燦めき、
秋は無数の秋津が白帆の羽根を棚引かせながら
銀河のように峠の頂を越えて行った。
その絶景の中で私は沢山の詩歌を書いた。
〈お前は天才だ〉と父は私を激励し、
思想家吉本隆明は私を〈天才詩人〉と称んだ。
*
あの日からすでに嵐のように半世紀が過ぎた。
世界文学の頂へ向けた新たな出帆の時が来たのだと、
私は今、吹き荒ぶ風の中で考えているのだ。

七線菊の物語
新城峠の麓の集落新城は、かっては林業で栄え、多数の人の出入りがあった場所として古くから知られていたようである。明治20年1月、青森県弘前町(現在の弘前市)に生まれた少年期の葛西善蔵は、明治36年から39年頃まで4年間、北海道を漂泊したことが知られている。その間の後半の時期に新城峠の東山と呼ばれるパンケホロナイ山の麓の伐採事業の頭領をしていた叔父を頼って新城の奥地に入り、一年余りを過ごしたという。葛西善蔵はその時の体験をもとに帰郷後、名作『雪をんな』を書いた。『雪をんな』は冒頭に空知川方面からパンケホロナイ川の上流を遡った奥所の村へ行き着く描写が為されていて、徐々に新城峠の秘境へと進み行く少年葛西善蔵の姿が鮮明に窺えるのである。
*
俳句を書き始めた十代の頃私は、新城峠に由来しこの地の村民たちによって伝えられてきた美しくも哀しい物語「七線菊の物語」を私の祖母で開基住職西川證信の妻ヒサから聞いた。
ヒサの話によれば、それは新城の開拓期の明治38、9年頃のことであったというから、丁度、葛西善蔵が新城峠を訪れた頃の出来事である。当時、新城では、峠を越える新たな道路を作る工事が行われ、本州方面から多数の人夫が連れられてきていたという。彼等はタコと呼ばれ、数ヶ月堀っ立て小屋に寝泊まりし、工事が終わると又、他地区の現場へと連れられて行ったという。
在る秋の日夜、峠に近い七線と呼ばれる地域の一軒の農家に母と娘が訪ねて来た。母は37、8歳。娘は11、2歳くらいで、歩き疲れていて、衣類もよれよれになっていたという。
事情を訊けば、遠く内地(本州)から父親を訪ねて来たという。
「この辺りに新城というところはありませんか。道路工事の現場で働いているという噂を人伝えに聞いたのです。」
農家の人はその母と娘を家に上げて泊め、母と娘は翌日から何日も何日も村中を足を棒のようにして訪ね歩いた。しかし、ついに父親の居場所は判らなかった。
ある日、農家の人は、思いがけない話を耳にした・それは、峠の道路工事が終わって他所に移る時、一人の人夫が家恋しさのあまりに逃げ出し、見つかって追われ、峠の麓で棒頭に殴り殺されたという噂であった。
どうもその殺された人夫が、母と娘が探している父親のようで、この話をしらたどんなに力を落とすかと胸を痛めた。だが、いつまでも黙っているわけにもいかず、ある夜、思い切ってこの話をしたという。
じっと話を聞いていた母と娘は、その場に泣き崩れ、一夜泣き明かした。
翌朝、母は泣きはらしたまっ赤な目に笑みをたたえながら、
「見も知らない私たちを随分親切にして下さいました。こんなにお世話になりましたのに、私たちには何もお返しすることが出来ません。せめてお礼にこれを」
と言って小さな袋の中から一握りの花の種を差し出して手渡しした。
母と娘は幾度も幾度も振り返っては頭を下げ、振り返っては又頭を下げて去って行った。
それから暫く経って、その年の初めての雪が降る頃、新城峠から14、5キロ離れた石狩川の神居古潭で身元の分からない母娘の入水自殺があったことを、農家の人は知った。
翌年になって峠の雪が解け、大地が緑色に染まった頃、母娘から花の種を貰ったことを思い出し、家の傍の畑に植えた。間もなく真っ白な清楚な花が咲いた。その花は年々殖えて、やがて七線道路いっぱい咲くようになった。誰ともなしにその花を村人たちは「七線菊」と呼ぶようになったという。
この物語を祖母ヒサから聞き終えた少年期の私は、その時、言い知れない哀しみと感動を覚え、私の心の中を一瞬、風のように流れ去ってゆくものを感じたことを今も忘れられずにいる。そしてこの物語は、その後も、私の辛くて暗い青春地獄の心の中に仄かに点った灯のように風に揺れ、或いは私の心の谷底にまっ白な一輪の野菊となって今も何処かに咲き続けている。
この白菊とは、実は自然の防虫成分を抽出する除虫菊であった。『新城町百年史』の記述に依れば、その後、新城は大正・昭和の戦前まで除虫菊の栽培が盛んとなって栄え、新城峠の丘じゅうが白い花で埋まり、新城の代表的な産業となって村を興し、除虫菊御殿と呼ばれる豪農が生まれるなど、海外からの視察者が訪れるほどにもなったという。
昭和二十九年から三十八年まで私の通った芦別市立新城小中学校の校章にもその花のバッチが確かに付けられていたのである。
この物語の文中にある「七線」とは、新城の森林が御料地で明治政府が名付けた区画整理による地区名である。私の在所は今も「六線」と呼ばれ、この物語の文中にある「七線」とは三丁ほどの距離しか離れていない。又「神居古潭」は北海道の代表的なアイヌ民族の聖地の名であるが、そこは切り立つ峡谷を流れる石狩川が最も急流となる難所で深い淵が到る所に渦巻き、此処での入水自殺者の亡骸は上がることはないと古くから云い伝えられてきた。しかし此処は十代の日の私が「創作ノート」を片手に自転車で新城峠を越え、幾度も訪ねた風光明媚の場所だった。
『幻想詩篇 天使の悪夢九千句』(2013年、茜屋書店)後記「白い渚を行く旅人」収載

帆柱
実存とは私の心の港の折れてしまった帆柱である。風来たりなば、魂の聲を出だす。
『風の言葉─西川徹郎語録集』(未刊)

〈詩〉とは何か─聲無き聲と十七文字の世界芸術
俳句は、日本が生んだ世界芸術である。寺山修司は、十代の日、青森の夜空へ向かって俳句を〈十七音の銀河系〉と叫んだ。彼は文学としての俳句革命を目指したが、西東三鬼等の抵抗に遇って挫折した。私は彼の遺志を継承し、以降半世紀に亘って季語季題の呪縛を破る〈反定型の定型詩〉実存俳句を書き続け、表現の荒野を闘い続けて来た。
与題の〈詩情〉や〈抒情〉と言った書き手の側のメンタルに詩の問題の根源的所在はない。そうではなく、〈詩〉とは何か。表現者に於る言語と存在に関わる必然的な哲学と思索のこの〈永遠の問い〉こそが、あらゆる詩歌や芸術に於る最も切実な火急の難題に外ならぬ。かつて思想家吉本隆明は、「言語表現の極北に挑」む未知の少年であった私を「俳句の詩人」と称(よ)んだ。
男根担ぎ佛壇峠越えにけり 徹郎 (『無灯艦隊』)
双手で耳を大きく蔽(おお)うても、我が身の奥所から絶えず聞こえてくるこの悲しみの聲を私はとどめることが終(つい)に出来ない。〈タスケテクレ〉、その聲はけして絶叫ではない。此の身の奥の扉の更にその奥の奥の内奥から込み上げてくる聲無き聲である。生の極限に立つ時、微かに聞こえてくるこの聲を聞きとどめ、更にこの聲を〈魂の幻影〉として書きとどめ得たものこそが詩であり、文学なのだ。更に云えば、人間存在のこの蔽いようのない悲しみの聲、根源的な悲哀のこの聲無き聲の聞こえぬものを私は詩とも文学とも認めることが出来得ぬのである。
「荒海や佐渡に横たふ天の川」、世界の詩の革命者松尾芭蕉! 絶望の果ての枯れ野で斃れつつある者の聲無き聲、詩と文学に全存在を賭けた者の悲しみの聲が満天の銀河に轟き渡っているのだ。
(『短歌年鑑 平成28年版』2015年 株式会社KADOKAWA収蔵)

少年期
銀河の何処か見知らぬ星に自分と同じ人間が必ず住んでいると信じて、私は十代の日々を過ごした。
(初出 『幻想詩篇 天使の悪夢九千句』茜屋書店・2013年)

秋祭
春祭は雪解けの遅れた年では未だ残雪が所々にあって、残雪に参道の幟が棚引く様子はさもさも北国の山峡の春の祭礼といった趣きである。
しかし、私には殊更秋祭が私の心の山峡の渓深く、幟棚引く哀愁の想念となって私の詩神の生成に関わってきたもののように思われる。
少年の頃、秋祭が来るとすぐ分かった。「ハタハタハタハタ」、参道の幟が強い秋風に棚引く声が朝夕、日夜絶え間なく庫裡の中じゅう鳴り響くからである。春祭にも同じ幟の声が聞こえはするが、空気の加減か気になる事はなかった。
だが、秋祭は私には殊更淋しかった。それは参道沿いの色付き電球のぼんやりした明かりのせいばかりではない。幟の棚引くその声が、夜明け頃になって漸く眠りに就く不眠症ぎみの私の浅い夢の中へまで無理矢理入り込んでくるからである。
(『無灯艦隊ノート』(1997年・蝸牛新社)
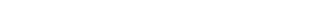
〈少年詩人〉と称ばれていた頃、私は石狩川の水の流れが殊更に好きだった。
夏休みはいつも自転車を駆って新城峠を越え、十四、五キロ北にある石狩川一番の急流で両岸が峡谷となって迫(せ)り立つ景勝地「神居古潭」へ出て、沢山の詩歌を作った。
そこは水の流れが無数の岩場をうねって渦を巻き、到る所に怖ろしきほどに波濤が上がっていた。
ある日、その川沿いの道を更に北へ進んで、私は遂に石狩川上流の白銀の大雪山系を北に望む、少年期のあこがれの都、美しき山岳都市旭川に到った。
日はすでに西へ傾き、広々とした石狩川上流の潺(せせらぎ)の波の刃に当たる夕陽の照り返しが、少年の眼を烈しく襲った。
夕映えは少年詩人の身体の髄までをも染め抜いて貫き、錚々とした水の流れは心を濯いだ。それは少年期の私の夢の果ての更なる果ての見知らぬ国の岸辺の小径だったが、私はただひたすら走り続けていた。
あの日からすでに半世紀が過ぎたが、今もなお私は詩歌や小説を書き続けているのである。果たしてあの日の岸辺の小径は、この世の径だったのであろうか。
美しき極北の山岳都市旭川の石狩川の岸辺に佇つ時、ふつと私の胸の奥の薄墨色の茜の中から自転車が現れて出て、その日の遠い記憶の中の夕映えの小径を私は幻の自転車で駆けめぐらせているのである。
エッセイ集『永遠の少年』(未刊)より
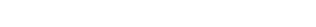
新城峠の麓の町新城へ開教に入った私の祖父で正信寺の開基住職しようしん證信は、道内各地へ布教に出る時は、神居古潭か芦別の駅から鉄道に乗る外はなかった。 芦別の町へ出るには、十四、五キロの峡谷の道を徒歩で越え、この空知の川を必ず渡らなければならなかった。北海道の開教期を代表する僧侶で京都の本山西本願寺でしようみよう聲明やごんしき勤式の指導者だった私の祖父西川證信は、若き日より清冽な信仰に燃え、七五歳の晩年に至る迄、雪に埋もれた暁闇の道無き道を越え、幾度この川を越えたことであろう。
かつて明治期に国木田独歩は、うら若き愛人信子を引き連れて、芦別岳の峡谷から流れ落ちるこの緑の川の岸辺をさ迷い歩いた。独歩は後に信子と離縁するが、小説『空知川の岸辺』を書き、文学の名声を後の世に残した。
独歩の若き日の名と共にこの川は緑の鏡となって岸辺を行き来する人々の生を映し出している。
葛西善蔵は少年の日、渡道し北海道を彷徨の果てにこの川を越え、北へ向かって新城峠を目指した。その途上、白魔に襲われて行き倒れになりかかったその日の記憶は、名作『雪をんな』を生み出したのである。
私の文学の果てなき道は、十代の日、祖父の書斎の薄暗がりから歌集、『一握の砂』初版本を見い出した時から始まった。
私はその歌集を密かに鞄に入れ、毎日、教師の眼を盗んで、中学校の教室の窓明かりを頼りに繰り返し読んだ。
私を文学の道へ誘ったその歌集は、何故に祖父の書斎に在ったのか。
その謎が解明されたのは後のことである。
私の祖父には実は、私の顔とよく似た西川しんぎよう信暁(1923~1941)という名の夭折した次男がいたと云う。私から云えば父證教の弟であり、叔父に当たる。親族は皆彼を「麿ちゃん」と愛称して呼んだ。彼は際立って頭が明晰で、しかも幼少の頃から常に書物を持ち歩き、床の中でさえ書物を読み、多数の和歌を大学ノートに書きつけていたと、後年、證信の妻ひさは私に語った。
空知川の緑の水のように、今も私の身体の中に流れ続けている血縁の生きて遂に相会うことのなかった夭折した歌人が、死に近き床の中でまで繙き読み続けていたというその書物こそは、かつて私が祖父の書斎で見出した一冊の歌集、『一握の砂』そのものではなかったのかと、私は今にして思うのである。
祖父は聲明のみならず、北海道随一の布教使でもあったから道内の当時の真宗寺院二百ヵ寺を隈なく巡回し布教した。北海道の寺院は夏の農繁期を避け、冬季間に法要が行われることが多かった。
祖父は暁暗に峠の寺を出て、雪に埋もれた道無き道を急ぐや、その胸には夭折した歌人たるわが子信暁への念いをひしと抱き締めつつ、氷雪のこの空知の川を幾度となく、否、幾千回となく渡ったことであろう。
私の文学は一言で云えば、日本随一の近代文学研究家であったかの文藝史家平岡敏夫氏が命名した〈夕暮れの文学〉であり、平岡氏に私淑した作家斎藤冬海の西川徹郎論「秋ノクレ論」の「秋ノクレ」の文学である。
〈夕暮れ〉、則ちそれは生と死の狭間、日と夜の、そして月と日の光の擦過する狭間である。
この淡く眩い光の交差の中に浮かび出づる十七文字の存在の幻影が、私の文学である。それ故、それは〈十七文字の銀河系〉であり、〈十七文字の世界藝術〉なのである。
しかるに私のこの十七文字の藝術は、薄っすらと血の色に染め上げられている。それはかの啄木へ羨望の念を抱きつつ夭折した我が子信暁の念いを胸にこの川を越えた若き日の我が祖父證信、うら若き愛人信子と岸辺をさ迷い歩いた国木田独歩、更には身籠もった幼き妻を旧里においた儘北海道を彷徨した葛西善蔵、彼らの若き日の胸はまさにこの地獄の火焔の如き北天の夕陽に焼かれていたからなのである。
〈畢〉
註
文中に出る平岡敏夫(1930-2018)氏は、日本の近現代文学の世界的研究家。筑波大学名誉教授で文学博士。北京・上海外国語大学大学院、ソウル・高麗大学大学院、台北・東呉大学大学院、アメリカ・デイキンソン大学等、アジア・ヨーロッパ・アメリカ等、海外の多数の大学の客員教授を歴任し日本の近現代文学の英華を海外へ伝えた。
平岡敏夫氏は、西川徹郞作家生活50年記念論叢『修羅と永遠│西川徹郞論集成』(2015年、茜屋書店)に「金子みすゞは何故死んだのか│西川徹郞小論」を発表した。
斎藤冬海は、かつて日本女子大学で平岡敏夫氏の直接の教授を受けた。平岡氏には『〈夕暮れ〉の文学史』『左幕派の文学』、詩集『月の海』等、極めて多数の著書がある。
文中に出る斎藤冬海執筆の西川徹郎論「秋ノクレ論│西川文学の拓く世界」四百枚は、『西川徹郞全句集』刊行記念論集『星月の惨劇─西川徹郞の世界』(茜屋書店)に収録されている。
本文「夕映の空知川」の初出は、2021年1月15日西川徹郞記念文學館発行の『西川徹郞研究』第2集(発売・茜屋書店)、本文は初出に多少加筆し掲載した。
なお、西川徹郎第二句集『瞳孔祭』(南方社)は、1981年、石川啄木『一握の砂』、国木田独歩『空知川の岸辺』、葛西善蔵『雪をんな』と共に『北海道文学全集』(立風書房)に収載されている。